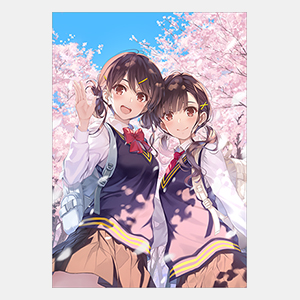- トップページ
- 双子探偵 詩愛&心逢 さようなら、私の可愛くない双子たち(1/2)
試し読み
双子探偵 詩愛&心逢 さようなら、私の可愛くない双子たち(1/2)
著:鈴木大輔
Interlude sideS-1
私はかつて双子の娘を捨てたことがある。
始めに断っておくが私は人でなしだ。血を分けた実の娘、腹を痛めて産んだ双子たちを捨てたことはもちろん、それ以外にも色々とやらかしてきた。天罰もすでに下っている。三十歳の半ばにして余命三ヶ月。まあ妥当な結果だろう。未練も本来、これといってないはずだった。
はずだった、というのはつまり、今は気が変わったということである。
ふと会ってみたくなった。捨てた娘たちに。
私は大慌てで準備を整えた。様々な小細工を施し、自分の素性も可能な限り隠せるよう手はずを整えた。ついでにちょっとした報酬とゲームも用意した。
娘たちは私が誰なのか気づくだろうか? それとも気づかないだろうか?
どちらでも構わない。むしろ気づかれない方が、良き人間にあるべき振るまいだろう。気づかれたとしても……それはそれで見物になるはずだ。どちらに転んでも私に損はない。
それにひとつ、娘たちに解いてもらいたい謎がある。十年の長きにわたって私には解けなかった謎だ。娘たちなら、あるいは解けるかもしれない。
私の名前? 【白雪日向】と名乗っておこうか。
双子の娘は白雪詩愛と白雪心逢。今ごろはきっと、私そっくりな美人に育っていることだろう。
マネージャーを連れて羽田行きの便に乗りながら、私は次第にうきうきした気分になってきた。
さすがの私もこの時に至るまで思いもしなかったのだ。
人殺しの罪に向き合うのが、こんなに清々しい気持ちになる行為だったなんて。
Day0
泣けなかった。母が死んだというのに。
病気が見つかってからは本当にあっという間だった。ほんの一ヶ月か二ヶ月。抗がん治療は拒否したから闘病生活と呼べる期間すらなく、みるみるうちに痩せ細っていっても『まあ人生こんなもんでしょ』と笑い飛ばす顔から生気が失われていくことはなかったし、レッドホットチリペッパーズと大江健三郎の話で盛り上がった翌朝にはもう母・白雪静流は眠るように息を引き取ってしまった。
故人の意思で葬儀は執り行わなかったからほとんど火葬場に直行だったし、書類仕事の手続きはあらかじめ母が依頼していた弁護士が黙々とこなしてくれたし、その弁護士がまだ存命していた祖母であったこともその流れで初めて知ったし、母の遺品の整理は専門の業者がビジネスライクに済ませてくれたし、祖母の家に引き取られることになった後は新しい土地と新しい学校での生活で手一杯になった。
気づいたら数ヶ月が経ち、白雪詩愛と白雪心逢は天涯孤独の身となった双子の姉妹として好奇の視線を向けられることにも慣れ、火葬場で嗅いだ魚が焼けるような遺骨のにおいも次第に記憶から薄れていった。
さらに五年の時が流れた。母の遺伝子はこの上なく自らの使命を果たしていたようで、詩愛と心逢の姿は若い頃の母に瓜ふたつとなった。
がしかし、それはただ本当にそれだけのことだ。元から母の交友関係は少なかったし、かつて暮らしていた東京都渋谷区とは縁が遠くなり、『一卵性の双子ってほんとに似てるんだね』と感心されることはあっても『あなたたちってお母さんに似てるんだね』と指摘されることはなくなった。母と絶縁状態にあった祖母は絵に描いたように寡黙で頑なな人で、実の娘にあたるはずの白雪静流について語ることは皆無に等しかったから、今となっては白雪静流という女性がかつて存在していたという事実は、すっかり輪郭のぼやけたものに成り果ててしまった。まるで壁に貼られたまま、陽に焼けて色あせてしまった写真のように。
今でもまだ、双子は泣けないでいる。
シングルマザーとして女手ひとつで育ててくれた母の死を、母の生を、うまく咀嚼できず飲み込めず、そもそも触れることさえできずにいる。とりもなおさずそれは、双子たちがまだ母の死という出来事を、宙ぶらりんのままにしていることを示してもいた。
それでいて興味を無くすわけにもいかなかった。いつまでもしつこく消えない熾火の炭のように微妙な気持ちを抱えつつ、それでいて母の死を何かの形で昇華したり、定義したり、ある種の再解釈を加えることもできないままでいた。
双子たちが血も涙もない娘たちだから、というわけではない。
それは彼女たちなりの自己防衛だった。涙を流さないのは自らの選択だった。少なくとも詩愛も心逢も、過去ではなく未来を向いて生きようとした。たとえそれが、母の存在を自ら遠ざける結果になるのだとしても。
そんな折だった。
ふたりのもとに奇妙な手紙が届いたのは。
†
その手紙が届く前の双子は、中学三年生の夏休みを退屈に過ごしていた。
日本の真ん中にある某県某市の、とある一軒家の、とある一部屋。
姉の詩愛は音楽を聴いている。
ヘッドホンで両耳を塞ぎ、天を仰ぐようなポーズでソファーにもたれかかり、盤上没我といった体で自分の世界にのめり込んでいる。リラックスとは真逆、まるで論文に矛盾を発見してしまった哲学者のように眉を寄せて、両目を閉じている。
妹の心逢は小説を読んでいる。
速読の彼女はページをめくるスピードが速い。左右の瞳が、ページの右から左へ、最新型の工業用ロボットみたいなリズムで小刻みに動く。ぺらり、はらり。ページをめくるかすかな音は、単調な中にもビードにうねりの利いた、ある種のジャズのようだ。
「ねえ詩愛さん」
先に苛立った声をあげたのは、妹の方だ。
「ちょっと詩愛さん。聞こえてますか? ヘッドホン外してもらえます?」
「……なーに?」不機嫌顔で姉の詩愛がヘッドホンを外す。「今いいとこなのに」
「音。漏れてます。詩愛さんのヘッドホンから」
「漏れないよ。これ遮音性の高いやつだし」
「漏れてますから。今ボリュームあげましたよね?」
「アルバムのいいところなのよ。【フラッシュバック】から【未来の欠片】」
「知らないですからそっちの音楽事情は。ボリューム下げてください。気が散ります」
「どんだけ神経質なの。そっちが耳栓すればいいじゃん」
「それは嫌です。気が散るので」
「じゃあ出てけばよくない? この部屋から」
「ここは心逢の部屋なので。出ていく理由がありません」
「心逢ちゃんだけの部屋じゃなくて、自分の部屋でもあるんだけど?」
「というか詩愛さん、部屋の片付けやっていませんよね」
「今日の当番は自分じゃないんで。心逢ちゃんの当番だし」
「詩愛さんは昨日サボりました」
「その前は心逢ちゃんがサボったじゃんか」
ふたりはにらみ合った。
すぐに視線を外した。
詩愛はヘッドホンを付け直し、心逢が小説に目を落とす。
家の事情でひとつの部屋を共有する姉妹も、夏休みの退屈に飽いて小競り合いする姉妹も、世にごまんといるだろう。
ただしこのふたりはやや事情が異なる。
第一に、彼女たちは一卵性の双子だ。姿形も声もよく似ている。今はお互いのしゃべり方に差をつけるようにしたため、さほどでもなくなったが、かつては姉妹の見分けがつかない人も多かった。髪型と服装をそっくりにしてお互いを入れ替えるいたずらも、過去に何度かやったことがある。
第二に、彼女たちには両親がいない。父親は最初から存在しなかったし、母親は五年ほど前に亡くなった。今は祖母の家に身を寄せている。
第三に――おそらくはこれが、詩愛と心逢がたまに小競り合いを始める最大の理由――部屋にモノが多かった。CDやLPやアンプやギター、小説に漫画に映画のDVD。結果、モノで部屋が圧迫される。圧迫されるとパーソナルスペースが狭くなる。狭くなると姉妹ふたりの距離が縮まって衝突が起きる。
それでも家庭の都合により、使える部屋はひとつきりだ。
仕方なくふたりは顔を付き合わせて、十畳サイズの部屋で時間を過ごすことになる。やりたいことはあっても先立つものがなく、何かを思いきるだけのきっかけもなく、家にあふれているコンテンツをひたすら消費するのに貴重な青春を費やす羽目になる。
それが双子たちにとって定番といえる長期休暇の過ごし方であり、来春に受験を控えているこの年の夏休みもそうなるはずだった。
†
事情が変わったのは某日の昼さがり。
夏日は続くものの、障子を開け放していれば涼しい風が通る。やや標高の高い場所にあるこの家は、冬は寒さが厳しいものの、夏は比較的過ごしやすい。
蝉しぐれ。
風鈴が奏でる音。
ぱらりぱらりと小説のページがこすれる音。
穏やかな顔で【D坂の殺人事件】のページをめくっていた心逢の眉が、あからさまにひそめられた。どたばたと聞こえるガサツな足音。姉の詩愛が外出から帰ってきた音だ。
「ねえ心逢ちゃん」
部屋に入るなり詩愛が話しかけてきた。
心逢は聞こえないふりをしてページをめくり続ける。
「ねえ心逢ちゃんってば」
「…………」
「聞けよ」ドンッ。心逢が座っているソファーの背中を蹴る音。
「……いま心逢は忙しいんですが? 邪魔しないでもらえます?」
「いつもどおり本読んでるだけじゃん。なんか変な手紙が来てんの。ほらこれ」
詩愛が差し出したのは、一風変わった封筒だった。
凝った作りがされている。紙は上質。あえてヴィンテージ感を演出した印刷。想起されるコンセプトはヴィクトリア朝時代に貴族の間で交わされた書簡――といったところだ。住所はわざわざ英語表記。ただし消印は普通に現代の日本のもので、東京都の渋谷区から投函されたものらしい。差出人の欄には【NAZO MAKER inc】とある。聞き覚えはないが、どこかの会社か法人なのだろうか。
「宛名は――白雪詩愛様、白雪心逢様。……心逢たちふたり宛に?」
「だね」
「詩愛さんは心当たりあります?」
「ない。てことは心逢ちゃんも?」
「ありません」
宣伝目的のダイレクトメール――にしては、どこか違和感があった。宛名も住所も手書きで書かれている。手当たり次第に一斉送付している郵便物、という感じがしない。そもそも封筒の作りがふるっている。ミステリに多少の心得がある心逢にとっては特に、興味を引かれる趣がある。
「開けていいのかな? これ」
「変な詐欺とかありますからね、今時は」詩愛に問われて、心逢はあごに手を当てて考える。「おばあさまに相談した方がいいんじゃないでしょうか。中身が何なのか気にはなりますけどね」
びりびり。
詩愛が封筒の封を破いた音だ。
「……ねえ詩愛さん。今の話聞いてました? なんであっさり手紙を開けたんですか?」
「爆弾が入ってるわけじゃあるまいし。別に開けても問題ないかなと」
「最初から開けるつもりならなんで心逢に相談したんですか」
「そりゃするっしょ。自分と心逢ちゃんの宛名になってるんだから」
「んもう」
心逢は小言を並べようとして、すぐに口を閉じた。
封筒の中から思わぬものが出てきたからだ。
新幹線のチケットが二枚。東京行きの。
それと招待状らしき紙がこれも二枚。名刺サイズの用紙には【リアル謎解きゲーム――“さようなら、私の可愛くない双子たち”】と記されている。
さらに便せんが同封されていた。
例によって手書きの文字でこう綴られている。
『招待状
白雪詩愛さま
白雪心逢さま
貴殿ら二名は当ゲームのテストプレイヤーに選ばれました。
つきましては、添付別紙に記載の日時に、待ち合わせ場所までお越しいただけましたら幸いです。詳細の儀は、当日に直接お会いした上でご説明させていただきます。
追伸:別途、現金書留を郵送いたしますので、旅費等としてご査収ください』
「……なんなんこれ」
「招待状じゃないですか?」
「だから何なんなのそれ」
「知らないですよ心逢に聞かれても。どこかのゲーム運営会社が送ってよこした手紙、ってことになるんじゃないでしょうか。今どきは多いですもんね、この手のリアルイベントって」
「ゲームのタイトルに双子って書いてあるっすね」
「それで私たちに連絡をつけてきた、ってことですか。それにしてもアナログの手紙でいきなり、というのはどうかと思いますが」
封筒からは別のものも出てきた。
使用済みとおぼしき絵はがきだ。十枚ある。それぞれにどこかの都会とおぼしき写真がプリントされている。
「……なんなんこれ?」
「絵はがきですね。リアルな」
「見ればわかるってそれは」
「リアル謎解きゲーム、って書いてありますから。それに使うアイテムか何かじゃないでしょうか」
「ふーん。ちょっと気になるかも」
「心逢にはもっと気になることがあります。現金書留を郵送、というのは?」
「ああ。これのこと?」詩愛は茶封筒を無造作に取り出して、「こっちも開けてみよ」
「あっ、ちょっとまた勝手に! 世の中には変な詐欺とかあるんですから、もっと警戒心を持ってですね――」
心逢のお小言はすぐに途切れた。詩愛も思わず目を丸くする。
現金書留の封筒には現金が入っているもの、と相場が決まっている。貯金箱の中に硬貨が入っているのと同じくらい自明の理だが――問題はその金額だった。
一万円札。
合計で十枚。つまり十万円。
まだ中学生の双子にとっては大金だ。
「え、ちょ。なにこれ」詩愛もさすがに焦った顔をする。
「旅費等としてご査収ください、って書いてありますから」心逢も声が震え気味。「もらえる、ってことですよね。このお金。心逢たちが」
「やばくないそれ?」
「やば……い気がしますよね、普通に考えると」
「やっぱ詐欺?」
「詐欺だとして、どういう種類の詐欺なんですかこれは? 普通に現金が受け取れてるわけですけど。こうやって実際に」
「自分らみたいな美少女を呼び出して誘拐して人身売買とか?」
「あり得ますね……美少女はいつの時代も犯罪に巻き込まれやすいものですから」
「じゃあ十万円だけもらって、ゲームのテストプレイとかいうのはガン無視しとく?」
「それはそれで怖いと思いますよ。こういうお金は受け取らずに返してしまうのが安全でしょうね」
「心逢ちゃん。そんなもったいないこと本気で考えてる?」
「いいえ。正直言うと心逢は、この十万円に目がくらんでいます。買いたい物がいくらでもありますから。それは詩愛さんも同じでしょう?」
「……んだねー。十万円はやばい。前から欲しかったもの買えちゃう」
「それにもっと正直に言うと、謎解きゲームのテストプレイにもちょっと興味があります。もっともっと言うと、ぶっちゃけ東京に行きたいです。夏休みをずっと田舎で潰すなんて、青春の無駄遣いにもほどがあるじゃないですか」
念のため調べてみたがお金は本物。
同じく新幹線のチケットも本物。
【NAZO MAKER inc】とやらも検索してみると、それらしきサイトがすぐにヒットした。新興の企業のようだが、過去に実績も十分にあげているらしかった。
双子は思いつく限りの議論を交わしたが、結論を出すことができなかった。
その日の夜。
夕食の場で祖母の意見を聞くことにした。
五年ほど前に母が亡くなってから、詩愛と心逢は母方の祖母にあたる人の元に身を寄せている。
しつけに厳しく、そのぶん口数は少なくてプライベートには思いのほか寛容。
好きなだけ音楽や読書をむさぼらせてくれる、詩愛と心逢にとってはありがたい保護者だが、いささか苦手な相手でもあった。“肉親と一緒に暮らしている”というより“死んだ母がかつて共に暮らしていた遠縁の家を間借りしている”という感覚が姉妹にはある。生前の母と祖母が絶縁の状態だった影響も、多分にあるだろう。
「あのう、すいません」
「実はこんな手紙が届いてまして」
ふたりは祖母に手紙を見せた。
祖母は黙ってそれを受け取り、目を通し始める。
そこはかとなく緊張が走る。学期末に成績表を見せる時みたいな。
そう、と祖母がつぶやいた。手書きの便せんを何度も読み返しているようだ。表情がひどく固い。
双子はそっとお互いの目を盗み見た。人生に疲れ切ってしまったような雰囲気が、この祖母にはある。中学三年生のふたりには、自分たちよりもはるかに年長の祖母が心のうちに秘めているであろう言葉など推し量れない。
そして長い長い間を置いてから祖母が言った。好きにしなさい、と。詩愛も心逢ももう子供じゃない、あなたたちの好きにしてみなさい、と。ただしなるべく小まめに連絡は入れること。東京に遊びに行けるからといって羽目を外しすぎないこと。
意外すぎる言葉だった。
何も期待していなかった――といえばうそになるが。【NAZO MAKER inc】に連絡を取りつけて確認なり照会なりを取ってみるとか、そもそも一切の関わりを持たないよう厳命するとか、もっと悪ければ警察に通報するとか、そんな対処をされると思っていた。
それがまさか好きにしなさい、とは。
好きにしなさいということは。十万円も、新幹線のチケットも、思うままにして良いということになる。
「江戸川乱歩全集!」
「はっぴぃえんど! LPで全部!」
部屋に戻るなり、双子は弾けるように盛り上がった。
「やっば! すっごいアガる!」
「ぜったい反対されると思ってたよね!?」
「ね!?」
両手でハイタッチ。
からの、両脚でぴょんとジャンプして、お尻とお尻を軽くぶつけ合う仕草。
「えーやばい。ホントやばい。ぜったい買います。江戸川乱歩の全集」
「自分もほしかったんだよね、はっぴぃえんどのLP。……ん? ていうか心逢ちゃん」
「え? なんですか?」
「江戸川乱歩の全集っていくらするの?」
「んー。心逢が欲しいのは二十万とかしますね」
「心逢ちゃんって頭いいのに算数できないの? 十万円じゃ買えないよそれ。自分のはっぴぃえんどは五万あればいけるんで。十万円を山分けしてぴったり五万円」
「なんですかそれ。かわいい妹のために十万円ぜんぶくれる、っていう発想はないんですか? 姉として恥ずかしくないんですか?」
「こういう時だけ妹ヅラするやつぅ。――ていうか新幹線! 東京!」
手紙の末尾には、待ち合わせの場所と時間が記されていた。
東京都渋谷区の某所。
ド田舎と呼ばれても反論できない土地に住んでいる双子にとっては夢いっぱいの大都会。およそ五年ぶりの、生まれ育った街。
「タダで東京に行ける!」
「ライブハウス行ってみたい! Quattroとか!」
「本屋さん行きたいです! アニメ専門店とかも!」
「渋谷のTSUTAYAでよくない? ぜんぶあるじゃんあそこに」
「それいい! ぜったい行きましょう!」
再びのハイタッチを交わし、双子はあわただしく旅行の準備に取りかかる。
……心に引っかかるものはあった。ひとつならず、とてもたくさん。
それでも沸き立つ感情は抑えられなかった。
もとより持て余し気味だった。ただでさえ中学生の少女であり、詩愛も心逢もそれぞれ強い趣味嗜好があった。“東京”の二文字はふたりにとって、目もくらむ魅力を放つ魔法の言葉だった。“リアル謎解きゲーム”のミッションも悪くない。刺激の足りない田舎の暮らしには、こういうスパイスがうってつけだ。
念のために待ち合わせ場所をGoogleで調べてみたが、ごく普通の喫茶店だ。祖母とも小まめに連絡を取るつもりでいる。セーフティーは十分に掛けているはずだ。
いい退屈しのぎ、いい小旅行になる。
この時はまだ、詩愛も心逢もそう思っていた。
【NOT FOR SALE】
試し読みの無断複製、転売、配布等は禁止します
© 2025 Kurehito Misaki, Daisuke Suzuki / TO Books.
「双子探偵 詩愛&心逢」シリーズのお買い求めはこちらから!

- 双子探偵 詩愛&心逢
- 著:鈴木大輔
イラスト:深崎暮人 - 定価:715円(税込)

- 双子探偵 詩愛&心逢 さようなら、私の可愛くない双子たち
- 著:鈴木大輔
イラスト:深崎暮人 - 定価:715円(税込)