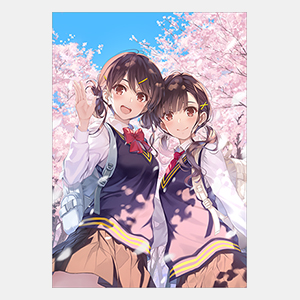- トップページ
- 双子探偵 詩愛&心逢 さようなら、私の可愛くない双子たち(2/2)
試し読み
双子探偵 詩愛&心逢 さようなら、私の可愛くない双子たち(2/2)
著:鈴木大輔
Interlude sideH-1
向き合おう。自分の罪に。
そう決めて私はこの手記を書きとどめることにした。
おそらく意味はない。誰にも読ませるつもりがないから。
だけどきっと正しいことだ。書き終えたら焼き捨ててしまうつもりの言の葉でも、心の内にとどめておくのと、文章にして著すことには、天と地ほどに違いがある。
――決めたはずなのに筆が重い。
私の本質は優柔不断だ。だけどこれからは違う。違わなければいけない。“彼女”のような私でいなければならない。奔放に、闊達に。万事を進めていく必要がある。
私は【白雪静流】。
白雪詩愛と白雪心逢、双子の子供たちの母親なのだから。
……そう自分に言い聞かせてみるものの、鉛を飲み込んだみたいに胃が重い。苦い液体がせり上がってきて、私は思わずその場でえずいてしまった。
ああもう、まったく。
人殺しの罪を背負うことが、こんなに息苦しい行為だったなんて。
Day1
目的地にたどりつくまでてんやわんやだった。
新幹線に乗るのさえ初めてだ。慣れない改札。自由席に指定席にグリーン席。
「指定席ってことはグリーン席?」
「グリーン席はお金持ちの席ですよ詩愛さん。そんなの常識でしょう?」
「でもこのチケットの番号ってこっちだよ、どうみても。グリーン席の方」
「うわ本当ですね。つまり心逢たちはお金持ちということですか」
「お金持ちなのは手紙の送り主ね。VIP待遇だわー」
十歳ぐらいになるまでは亡き母と東京で暮らしていたから、電車は何度も乗っていたが。新幹線はシンプルに速かった。それに静か。
「うわすっご。文明の利器だこれ。お値段お高いのも納得」
「見てください詩愛さん。ここにコンセントがあります。スマホ充電し放題です」
「あれっ? 車内販売ってもう存在しないの? ショックすぎるんだけど」
「ショックというか何も買ってきていないんですが。食べるものも飲むものも」
「だから言ったじゃん、おやつは買っておいた方がいいって」
「詩愛さんだってノリノリだったじゃないですか。十万円あるし車内販売で王様気分を味わうぜー、とか言って」
ぎゃんぎゃん騒いでいると隣の客に睨まれた。詩愛はあわててヘッドホンで耳を塞ぎ、心逢は素知らぬ顔で文庫本を開いた。
少しの着替えと最低限の日用品を詰め込んだカバンを持って、東京駅まで一時間ちょっとの旅。これだけでもかなりの満足感があった。
東京駅から日比谷線に乗り換え。
広尾駅からは徒歩。かつて住んでいた渋谷区の区内で――双子にとってこのあたりは、ちょっとした縁のある場所だ。
「ゴチャついてるねえ、このへんって」
「渋谷って大体どこでもこんな感じじゃないですか。心逢たちが住んでる今の場所が田舎すぎるだけで」
「でっかい建物もある。あれ大学か何か?」
「病院ですよ。日本赤十字医療センター」
「あー……。そうだった。忘れてた。ちょい懐かしい」
「いま見ても本当に大きい病院ですね。ひとつの街ぐらいありそうです」
待ち合わせの場所は、その巨大病院のすぐ近くにあった。
歴史を感じさせる外観の喫茶店。こぢんまりとした店構えに色あせた木製のドア。ドアの隣にはガラス張りのディスプレイ。ディスプレイの中に、ホコリを被った食品サンプルのクリームソーダ。
双子はお互いに顔を見合わせてからドアを開けた。
†
待ち合わせの相手はすぐにわかった。
理由はふたつ。
ひとつには、その時間帯の喫茶店に他の客が誰もいなかったこと。
そしてもうひとつには、その人物の見た目があまりにも怪しすぎたこと。
「やあどうも。こんにちは」
依頼人らしきその人物が手を挙げてあいさつをしてきた。おそらくはにこやかに。
おそらくというのは、その人物が大きなサングラスをかけていて、同じく大きなマスクで顔を隠していたからだ。真夏だというのにトレンチコートまで着ている。しかもコートの下に重ね着でもしているのか着ぶくれしていて、本来の体型が読み切れない。ご丁寧に頭にはフェルトハットまで被っていて、髪型さえ判然としない。さながらハードボイルド小説に登場する、探偵みたいなファッション。薄暗い店内の雰囲気も相まって、コスプレだとすれば完成度はかなり高い。
「白雪詩愛くんに白雪心逢くんだね? さあどうぞ座って。それと注文を。好きなものを頼んでもらって構わないよ」
くぐもった聞き取りづらい声で、その人物は手招きしてくる。四人席の向かい側に座れ、というゼスチャーなのだろうが、
「えーと……」
詩愛が困惑しながら妹に耳打ちした。
「どゆことこれ? もう“始まってる”ってこと?」
「そう……なんじゃないですか?」
心逢も困惑しながら姉にささやいた。
「リアル謎解きゲーム、ってことでしたから。いわゆる“形から入る”ってことなんじゃないでしょうか」
「キャラ作りの一環?」
「たぶ……ん?」
「さあどうぞ」待ち合わせ相手が再び促してきた。「座ってくれないと話もできない」
双子は席に着いた。かなり腰が引けている。
「注文は好きなものをどうぞ。そのあとでさっそく本題に入ってもいいかな?」
「いや全然よくないっす」詩愛が即答した。「もうちょっといろいろ説明してもらえないっすか? 自分らほとんど何もわからずここに来てるんで」
「ゲームのテストプレイ、ってことでしたけど」心逢も続いた。「具体的にはどんなことを? というか他には誰もいないんですか? 私たちふたりだけ?」
「最初に確認しておかねばならないね」
依頼人がメニュー表を差し出しながら言った。
「ルールその一。この場の主導権は私にある。質問は好きにしてもらって構わないが、私がそれに答えるとは限らない。また正しい答えを口にするとも限らない」
「……というルールのゲーム?」詩愛が眉をひそめた。「ってことっすか?」
「ルールその二。私の発言をどう解釈するかは君たちの自由だ」
ロールプレイング、という概念がある。
いわゆる“キャラのなりきり”。詳しくはないものの、サブカル絡みの界隈にそういう概念があることぐらいは、双子もぼんやりと知っていた。
招待状の送り主は、目の前にいる人物とみて間違いなさそうだが……見た目もしゃべり方も仕草もすべてが大仰すぎる。少なくとも、現実に存在する人物の素の姿であるとはとても思えない。
詩愛と心逢は顔を見合わせてアイコンタクトを取った。このあたりは双子の呼吸の妙、普通の人間よりは気息が通じる。
さしあたりは言い分を聞いたところで実害はなさそうだ、と彼女たちはみた。依頼人から渡されたメニューを開いて注文を物色し始める。
双子たちの反応を肯定と受け取ったのだろう。依頼人が続けた。
「ルールその三。依頼を受けるのも受けないのも君たち次第、途中でやめるのも続けるのも君たち次第。それと前金はもう君たちのものだからね、好きに使ってくれていい。依頼を成し遂げたら後金も払おう」
「気前が良いんですね」心逢が言った。「本当にもらってもいいんですか? あの十万円。未成年に払う金額としては多すぎないですか? 領収書とか要らないんですか? 【NAZO MAKER inc】とかいう会社か何かの人なんですよね?」
「とても良い見立てだし、とても良い質問だ」
くぐもった声で依頼人は笑った。マスクをしているせいもあるのか、やはり声が聞き取りづらい。
「だがここでもうひとつの確認をしておこう。ルールその四。“私の正体を詮索しないこと”。それがこの依頼の前提条件だ」
依頼人の手元にはコーヒーカップが置かれている。アイスではなくホット。とっくに冷めて湯気は出ておらず、口をつけた形跡もない。
「私は謎の依頼人として君たちに接する。それが納得できないなら話はここで終わりだ。適当に渋谷の見物でもして家に戻るといい。前金の十万円も返さなくて結構」
「……気前、本当に良すぎません?」
「だが興味は湧いてくるだろう?」
心逢はくちびるをひん曲げた。図星を突かれている。
「お金の心配はしなくていい。滞在にかかる費用の一切はこちらで出す。宿泊先の手配も任せてもらおう。一日や二日ではこなせない依頼になる。連絡先はあとで交換。ビジネス上のやり取りはそれで済まそう」
詩愛と心逢はふたたび顔を見合わせた。
不安と戸惑い。それに勝る好奇心。
うまい話には裏があるというが、今のところ危険な雰囲気は感じない。手を挙げて店のスタッフを呼ぶ。詩愛がクリームソーダを、心逢がカフェオレを注文する。
「さて肝心の依頼の内容についてだが。絵はがきは持ってきてるね?」
「手紙の中に入ってたやつっすか?」
十枚の絵はがきをテーブルの上に広げた。
双子はあらためてそれらを眺める。
「で、なんなんすかこれ?」
「どうぞ。手に取ってみて」
言われたとおり、あらためて手に取ってみる。
絵はがき。十枚。絵柄はまちまち。どうやら都会の光景をプリントしたもの、ということは共通しているようだが、それ以外の共通性はパッと見ではわからない。
裏返してみた。消印が押されていることからして、使用済みの絵はがきだということはわかる。宛先はすべてアルファベット表記。日本から海外に向けて発送されたものだが、差出人の名前も受取人の名前も書かれていない。
「この絵はがきの謎を解いてもらいたい」
依頼人は言った。
「それが君たちへの依頼だ」
「謎……って言われても」心逢が首をかしげる。「この絵はがきの何が謎なんでしょうか? 普通の絵はがきに見えますが」
「差出人の名前と受取人の名前が書かれてないのはまあ、ちょっと変かな」詩愛も眉をひそめる。「でもそれだけって言えばそれだけにみえる」
「それも謎のうちさ」依頼人が肩をすくめた。「君たちが解くべき謎にふくまれる」
「ヒントは? 他にないんです?」と心逢。
「とっかかりが何もなさすぎるよね」相づちを打つ詩愛。
「いま現在、君たちに示しているものがすべてだ。この条件で謎を解いてもらう。そして謎の回答を提示できるのは一度きりだ。何度も誤答を繰り返して正解にたどり着く、という道のりはたどれない。一発勝負で決めてもらう。その方が自ずとゲームの緊張感も湧いてくるだろう?」
双子は顔を見合わせる。
ゲームというならば、確かにそういうルールの設定も妙味か。そもそも否やを口にできる立場でもない。やめるも続けるも自由、と言われてもいる。
「それともうひとつ条件をつける」依頼人は淡々と告げた。「ペナルティを設定しよう。謎解きが一日遅れるごとに、君たちにはリスクを負ってもらう」
「えっ」
「なんですかそれ」
詩愛と心逢は警戒をあらわにした。
あやしい見た目をした依頼人の、意味のよくわからない依頼だ。金払いが良すぎるほど良いだけに、どんな要求をされても不思議ではない。双子の美少女に対する理不尽な要求といえば、いかがわしいことと相場が決まっている。詩愛と心逢が身構えるのも当然だったが、
「ペナルティは君たちの魂」
「え?」
「は?」
依頼人の提案は想像の斜め上をいっていた。
発言の真意をはかりかねる。返答の仕方が思いつけない。双子はふたりして口をつぐみ、お互いと依頼人とへ交互に視線を向けている。
「ただの比喩表現さ。物理的に君たちの命を頂こうと言ってるわけじゃない」
そんな双子の心理を見越したように、依頼人が笑う。
「具体的にはね、君たちの話を聞かせてもらおうと思っている。もちろんただの雑談ではペナルティにならない。君たちの心のうちを晒してもらおうか。たとえば君たちが普段はとても口にできないような秘密――なんかはちょうど良い。そういった秘密は得てして身を切るものになる。ある意味では魂と引き換えと言ってもいいだろう」
「心のうちを晒す……?」
「秘密って言われても……」
双子はふたたび困惑する。そんなものを聞いて、この依頼人にとって何になるというのだろう。リアル謎解きゲームとやらに何の関係があるのだろうか。単なる変質者であれば、中学生女子の秘密を知りたがるのは普通の思考かもしれないが、そもそも何をもって秘密だと判断するのだろうか? 心逢と詩愛が適当な話をでっちあげたとしても、依頼人にはわかりようがないのでは?
「何を君たちの秘密として語るか、あるいは何をもって秘密と定義するか。それも君たちに任せる。この条件で依頼を受けるかどうかも、もちろん君たちに任せる」
「期限は?」と心逢。「いつまでに謎を解けばいいんですか?」
「私がこの街を離れるまでに」
「いつこの街を離れるんですか?」
「言わない。意外と長く居るかもしれないし、ある日ふらっと街を離れるかもしれない。その場合でも前金を返せとは言わないよ。……ああそうだ、後払いの報酬の話がまだだったね」
依頼人は人差し指を一本立てた。
ご丁寧に、手には黒い手袋がはめられている。自分の正体は何が何でも隠すという意思が強く伝わってくる装いとみえる。
そして依頼人は条件を提示した。
「一億円」
双子は固まった。
詩愛は口をぽかんと開け、心逢は目を丸くしている。
「ひとりで一億円。ふたりで二億円。謎が解けたら報酬として渡そう。金額が金額だからね、支払い方は依頼が解決した後で相談するのがいいだろう。それと今のうちに連絡先を交換しておこうか」
言われるままに詩愛と心逢はスマホを差し出した。あまりに巨額の報酬を提示されて、思考が停止してしまっていた。
連絡先を交換してから依頼人は立ち上がった。まるで老人みたいな、ひどくゆっくりとした動作だった。
「話は以上。明日また同じ時間にこの場所で会おう。君たちが姿を現さなかったら、その時点で依頼を放棄したとみなす。明日まだ謎が解けていなかったら君たちにはペナルティを支払ってもらう」
依頼人が微笑んだように見えた。
サングラスにマスク、夏にそぐわない着ぶくれたトレンチコート。これだけでも意外なほど素性が隠せるものだと、詩愛と心逢は妙なところで感心した。
「さあゲームの始まりだ。君たちが楽しんでくれることを祈っているよ」
【NOT FOR SALE】
試し読みの無断複製、転売、配布等は禁止します
© 2025 Kurehito Misaki, Daisuke Suzuki / TO Books.
「双子探偵 詩愛&心逢」シリーズのお買い求めはこちらから!

- 双子探偵 詩愛&心逢
- 著:鈴木大輔
イラスト:深崎暮人 - 定価:715円(税込)

- 双子探偵 詩愛&心逢 さようなら、私の可愛くない双子たち
- 著:鈴木大輔
イラスト:深崎暮人 - 定価:715円(税込)