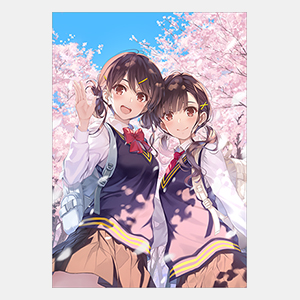- トップページ
- 双子探偵 詩愛&心逢(1/3)
試し読み
双子探偵 詩愛&心逢(1/3)
著:鈴木大輔 イラスト:深崎暮人

「……ま、自分らにかかればこんなもんかな!」
手鞠坂女子学園、学生寮【叢風館】の一室にて。
学園新聞を広げながら、白雪詩愛はご満悦の表情でうなずいた。
「悪い気はしないねえ。【快進撃!】【飛ぶ鳥を落とす勢い!】……どちらも承認欲求をくすぐってくれるワードだし。【美少女双子姉妹!】ってアオリも“わかってる”感あるっていうか。この記事を書いた新聞部の人、才能あるなァ」
「見る目がありますよね、この学校のみなさんは」
同じく学園新聞を広げながら、白雪心逢はふんぞり返った。
「もっとも、わたしたちが目立っているのは単なる事実ですけど。コンテストで金賞を取って、小説賞で入選して――立てば芍薬、座れば牡丹なのも事実ですし、廊下を歩くだけでも視線を集めるし。もはやアイドル扱いですよ。学園新聞で持ち上げられるのも当然の結果と言えますね」
白雪詩愛。
白雪心逢。
この年の春、手鞠坂女子学園に入学したばかりの、双子の姉妹だ。
「入学してたったの一ヶ月!」
「それでいて学園内で注目の的!」
二人部屋の学生寮【叢風館】にて詩愛と心逢は同室。近代的な建築で、生徒のプライベートに配慮して防音も万全。少しばかり騒いだところで話し声は外に漏れない。
「コンテストで金賞!」
「小説賞で入選!」
「入学デビュー大成功!」
「人生バラ色!」
六畳一間の密室で、双子たちは意気軒昂だった。その姿には、学園新聞で褒められた奥ゆかしさはこれっぽちも見られない。
「それゆけ白雪姉妹のお通りだ!」
「双子が通れば道理が引っ込む!」
「美しいだけでなく奥ゆかしい!」
「そのうえ才能まであってすいませんね!」
「選ばれし者たち!」
「ノブレス・オブ・リージュ!」
いえーい! と。
ジュースの入ったコップを高々と掲げ、双子はハイタッチを交わす。
晩春の夜。夕食もお風呂も宿題も済ませ、エアコンの効いた部屋で喉を潤す黄金色のりんご果汁は、まるで未来を祝福するかのように甘い。
そうしてひとしきり高揚感を味わったふたりは、どちらからともなくため息をついた。
はあ。ふう。
肩を落としてうなだれる双子の姿は、ほんの一秒前とは打って変わって重い。
「……いやー。ちょっと過大評価されすぎじゃないかなー?」
詩愛が頭をかいた。
「金賞って言っても、真ん中よりちょっと下、ぐらいの賞なんだけど。参加してた人も少ないし、見に来てるお客さんも少ないし」
「そっちはまだマシですよ」
心逢が恨めしそうに姉を見る。
「わたしの入選なんて、参加賞に毛が生えたぐらいのものですから。運営のお情けで頂いてる賞です。もらえたのは百均の文房具コーナーで売ってるノート三冊」
「モノをもらえただけまだマシじゃん。自分なんてひどいよ? 主催者の人と握手して、写真撮っただけ」
「わたしの短編小説は二週間ぐらいかけて新作を書いてますから。詩愛さんが演奏した曲って、だいぶ前に作ったやつの焼き直しでしょう? かけてる労力が違いすぎます」
「自分だって練習はちゃんとしてるし」
「ワンパターンのコード進行だけでゴリ押ししてるギターソロのことですか? この間のコンテストも、絶対ミスしない自信のあるアルペジオを適当に鳴らしてお茶を濁してたんでしょう?」
「心逢ちゃんだって、元ネタばればれのでっちあげ短編だったじゃん。乱歩の【屋根裏の散歩者】のパクリっしょ? あれでよく参加賞だけでももらえたよね。予備審査で落とされなかっただけ感謝するべきなんじゃね?」
詩愛と心逢はにらみ合った。
おでことおでこがくっきそうなぐらいに顔を寄せ、眉間にしわ作り、くちびるをひん曲げてメンチを切っている。その姿は控えめに言ってもブスだった。【美少女双子姉妹】の看板は見る影もない。
「……はあ」
「……ふう」
ため息をついて双子たちは矛を収める。不毛な争いをしている自覚を持てる程度には、まだ彼女たちは冷静さを保っていた。
「実際のところどうなんかな?」
「どうなんかな、って何がです」
「過大評価の話。いつの間にこんなことになっちゃったかなあ」
「まさにいつの間にか、ですよ。心逢たち、ごく普通の新入生だったつもりなんですが。高校デビューしてやろう、みたいな気持ちも別になかったですし」
「やっぱ目立つのかな双子は」
「似てますからね、心逢と詩愛さんは。見た目そっくりな女子高生が並んで歩いてたら、やっぱりみなさん振り返ってきますよ、学校の中でも外でも。高校に入る前までは田舎暮らしだったから、そんなに注目はされなかったですけど」
「東京に出てくるとアレかな、やっぱ美少女は周りが放っておいてくれないんだね」
「その点は否定できないでしょうね」
ふたりして腕組みをし、難しい顔をする。
「けっきょく心逢たち、キャラが立ってた、ってことだと思うんですよ。見た目そっくりで、顔も良くて、片方は音楽やってて、もう片方は小説やってて。しゃべり方までキャラづけしてますからね」
「その点は心逢ちゃんだって人のこと言えないっしょ? 誰に対しても丁寧語しゃべりしてるじゃん。ちょっとでも自分を賢くみせようとしてさ。背伸びしてもいいことないと思うんだけどねえ」
「ケンカ売ってます?」
「買ってくれるなら売りますケドー?」
にらみ合った。
すぐやめた。そして再びの難しい顔。
「あとはアレかな。自分らだいぶ調子に乗ったんで……」
「それはありますね……最初から『なんかすごい人たちかも?』みたいな扱いをされたから、ついついその波に乗っちゃったというか……【天才美少女双子姉妹!】とか言われて、うっかりその気になってしまったというか……」
「学園新聞のインタビュー受ける時もめっちゃドヤ顔してたもんね、心逢ちゃん」
「詩愛さんのドヤ顔も相当なものでしたけど? 両手でろくろ回す仕草しながら得意げに受け答えしてましたよね?」
「ケンカ売ってんの? ……いやそんなこと言ってる場合じゃないか。これからどうする?」
「どうする、とは?」
「このキャラのままでいくのか、ってこと」
詩愛が渋い顔をする。
「今ってなんか、周りからホントにアイドルみたいな目で見られてるし。このままだとだらしない格好とかできない雰囲気だし。授業中に居眠りしたりとか、教室であぐらかいたりとか、スカートの下から下敷きで風を入れたりとか」
「ホントそれですよね……」
心逢が悩ましげな顔をする。
「注目の的になるって、いいことばかりじゃないといいますか。心逢たち、普通の友達とかいないですもんね。周りにいるのはファンとか信者みたいな人ばかりで。基本的には遠巻きに見られてるし」
「だよねー。そういう人たちがアイドル扱いしてくれるもんだから」
「わたしたちもつい、調子に乗ってしまうというか」
「調子に乗ると、なんか“ちゃんとしてなきゃいけない空気”みたいなのを感じ始めるんだよね」
「ホントそれです。一種の同調圧力なんですかね? とにかく肩が凝りますよ、周りから妙な期待をされてる状況というのは」
「それにアレだよね。自分らって“ふたりでひと組”みたいに数えられてるっぽいというか。“あのふたりは絆が強いはずだから割って入るのは遠慮しよう”みたいな空気あるというか」
「おかげで地味にぼっちなんですよね。人気はあるのに」
「お昼ごはん食べてる時も、いつも自分らふたりだけ。周りの人たちはそれだけでキャーキャー言ってくれるけど」
「期待されすぎるのも重たいんですよ。みなさんってもしかして、心逢たちが芥川賞とかグラミー賞でも取ると思ってるじゃないですかね? いや取れないですから。あと十年ぐらいは」
双子の愚痴が続く。
はあ、とため息をついて、ふたりはアンニュイな気分で天井を眺める。甘かったはずのりんごジュースがやけに酸っぱい。
「……まあ、でも」
天井を眺めながら詩愛がこぼす。
「チヤホヤされるのって、オイシイよね」
「ぶっちゃけそれはありますね」
同じく天井を眺めながら心逢が同意する。
「キラキラした目で見られるのって、シンプルに気持ちいいっていうか」
「めちゃくちゃわかります。プレゼントとかもらいますよね、たまに」
「そうなんだよねー。このあいだもらった手作りのクッキーとか、地味にありがたかったなー……自分ら育ち盛りなんで。いつもお腹べこぺこなんで」
「“ふたりで一組”っていうのも、あながち間違っていませんしね」
「まあ最悪、自分らふたりだけでぼっち、っていうのも悪くないかもね。高校三年間ずっとそれなのはどうかと思うけど」
「まあゆっくりのんびり、でいいんじゃないでしょうか? 塞翁が馬、って言葉もありますし、きっとこれもいい経験でしょう。わたしたちの目的さえ忘れてなければ」
「そーね。そのうち誤解も解けていくっしょ。自分ら、アイドル的なポジションあんま向いてないし。勝手に化けの皮が剥がれていくと思うな。自分らの目的さえ忘れてなければ何でもいいか」
白雪詩愛と白雪心逢。
双子の姉妹はちょっと美人で、ちょっと才能もあって、わりと調子乗りで、そしてまあまあ図々しかった。
「じゃ、いけるところまでいっちゃいます?」
「そうしてみましょうか。周りから求められてるわけですし、祭り上げられてみるのも悪くないかと。立場が人を作る、みたいな言葉もありますしね」
「ところで何なの【探偵】って。自分らそんなことやったっけ?」
「あれですよたぶん。このあいだ助けてあげたじゃないですか。学生寮で困ってる人がいて――」
「あー、あれか。いやでも人助けぐらい誰でもするっしょ? 自分ら大したことしてなかったよね? あんなので【探偵】とか言われてもなァ」
「ていうか“とある情報筋”って何ですか。どこの誰が何の筋の話をしてるんでしょうね?」
「ま、どっちでもいいっしょ。こっちは乗れるだけ乗っかっていくだけなんで。……ていうかギターの練習しよっと。金賞取ったぐらいじゃ話にならないしね、実際」
「まったくです。わたしも次回作のプロットを考えます。入選なんて、何も成し遂げていないのと同じですから」
†
ひとしきり“作戦会議”を済ませてから、詩愛はギターを手に取り、心逢はノートパソコンを開ける。
この時のふたりはまだ、甘くみていた。
詩愛も心逢もちゃんとは理解していなかったのだ。
私立手毬坂女子学園の、ちょっとばかり特有な事情を。
学園内で目立ちまくっている双子の新入生、という存在が、想像以上に一人歩きし始めて、ことのほか大きな影響力を持つに至るという未来を――当人たちはまだ、知るよしもない。
【NOT FOR SALE】
試し読みの無断複製、転売、配布等は禁止します
© 2025 Kurehito Misaki, Daisuke Suzuki / TO Books.
「双子探偵 詩愛&心逢」シリーズのお買い求めはこちらから!

- 双子探偵 詩愛&心逢
- 著:鈴木大輔
イラスト:深崎暮人 - 定価:715円(税込)

- 双子探偵 詩愛&心逢 さようなら、私の可愛くない双子たち
- 著:鈴木大輔
イラスト:深崎暮人 - 定価:715円(税込)