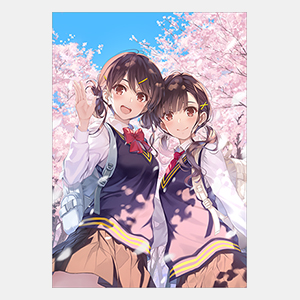- トップページ
- 双子探偵 詩愛&心逢(3/3)
試し読み
双子探偵 詩愛&心逢(3/3)
著:鈴木大輔 イラスト:深崎暮人
その女性のことを、双子たちは【マネさん】と呼んでいる。
外国の人ではない。画家のエドゥアール・マネに縁があるわけでもない。【マネさん】は【マネージャーさん】の略称である。初めて出会った時、彼女の肩書きがマネージャーであったため、そのまま略称が定着してしまった。
見た目は二十代の後半。クール系のメガネ美人。
出会ってからまだ一年足らずであり、手鞠坂女子学園に入学するまで何かとバタバタしていたために、双子たちはまだマネさんのことを詳しくは知らない。が、いくつかハッキリ判っていることもある。
ひとつには、彼女が大変に有能な人物であること。
ふたつには、彼女が多岐にわたる技能を有していること――編集者、クリエイター、プロデューサー、経営者、管財人など様々な顔を持ち、双子たちが知らない顔もまだ持っているらしいこと。
そしてみっつめ。彼女は成り行き上、白雪詩愛と白雪心逢の後見人的な立場を買って出てくれていること。
「……と、いうわけなんですが」
通話であらかたの事情を話し終えた。
学生寮【叢風館】、詩愛と心逢の二人部屋。
飲みかけのりんごジュースはもう、人肌に近い温度にまで温くなってしまっている。
『なるほど』
スマホの向こうでマネさんは頷いた。
液晶画面に映るマネさんは寝間着姿だが、クール系美人の雰囲気はいささかも損なわれていない。
『なるほど』
もう一度マネさんは頷き、口元に手をやって黙り込んだ。絵に描いたような沈思黙考の姿だ。
詩愛と心逢は顔を見合わせる。マネさんが考え込むのはめずらしい。基本的に即断即決の人である。もちろん闇雲に動くわけではなく、シンプルに頭脳明晰で行動力があるゆえの即断即決だ。ブルドーザーのように荒れ地を平らにしながら同時にアスファルトで舗装していく――そんなマネさんの姿を、双子たちは何度も目にしてきた。
『ややこしい――』
しばらくしてマネさんが口を開いた。
『とてもややこしい、込み入った話になってしまったようですね』
「……っすよね!」
我が意を得たり、とばかりに詩愛が身を乗り出す。
「いやー、やっぱり難しいっすかマネさんでも。ホントわけわかんない状況っすよね、これって。謎だらけで意味わかんなくて、謎が謎を呼ぶ、みたいな」
「すいませんマネさん、こんなことまで相談に乗っていただいて」
心逢もすかさず乗っかかる。
「単なる愚痴だと思って聞いていただければ十分なんです。ブレインストーミング、というやつですか? 話しているうちに何かヒントが思いつくかもしれないな、みたいなことを目論んでいたといいますか。ねえ詩愛さん?」
「そうそう、そうなんすよ。こんな訳わからない状況を通話で聞いただけで解決しろだなんて、そんな都合の良いことは考えてないっすから。あくまでもご相談っすからね、あくまでも」
「あとは近況報告ですね。わたしたちこんなことになってます、っていう。あ、別に自慢してるわけじゃありませんよ? アイドル扱いは気持ちいいですけど、何かと苦労も多いですし」
「心逢ちゃん。そんな言い方すると逆にアピールしてるみたいに聞こえるって。忙しい自慢とか寝てない自慢みたいに思われるって」
「確かにそれもそうですね。……すいませんマネさん、うちの姉にご無礼な発言がありまして」
「えっ? なんでこっちが悪いみたいな話になってんの?」
双子がケンカを始めそうになった。
マネさんが割って入った。
『すいません誤解を招く言い方でしたね。わたしはこう言いたかったんです。謎はもう解けていますよと』
双子は黙った。
それから「えええええっ⁉︎」と声を揃えた。
「謎が解けた⁉︎ 今の話を聞いただけで⁉︎ っすか⁉︎」
「そんなまさか……マネさんは美人で多才なだけでは飽き足りず、安楽椅子探偵でもあっただなんて……これじゃ面目が丸つぶれじゃないですか……一応はミステリ好きを自称している心逢としては……」
『ああすいません。今度は言い方が短絡的すぎました』
画面の向こうでマネさんは苦笑いを見せる。
『もう少し正確に伝えさせてください。そもそもこの話、わたしの視点から見ると謎でもなんでもないんです。お二人に“知らないことが多すぎる”から、まるで謎があるかのように見えてるんですよ。……いえ、すいません。お二人の顔を見るに、これでもやっぱり言い方を間違えていますね』
「……どんな顔してるんすか? 自分らって」
『狐につままれたような顔を』
双子たちは両手で自分たちの顔を触り、お互いに顔を向け合った。
なるほど、ポカンとした顔をしている。狐狸に化かされた、と表現して差し支えなさそうな間抜け面だ。『お二人はリアクションが優れていますね』とマネさんが言った。おそらく褒めてくれている、もしくはフォローしてくれているのだろうが、詩愛も心逢も素直には喜べなかった。
「ええとそれで」と詩愛。「結局どういう話なんすかね、これって? 自分らの置かれてる状況って何なんすか?」
「目安箱の意味はどういうことなんでしょう?」心逢も加わる。「三通の投書、三通りの筆跡、三人の人物への調査依頼――誰が置いたのかもわからない目安箱。マネさんの話だと、大体の見当はついている、という理解でいいんですよね?」
『その件なのですが』
マネさんが笑った。
スマホ越しでもはっきりそれとわかるくらい、いい笑顔だった。双子たちがこれまで見たことのない、有能クール美人の絵に描いたような破顔である。付け加えるならちょっといたずらっぽく、意地悪げでもある。
『この問題はぜひ、お二人で解決して頂きたく。ひょんなことから面白いことになっているみたいですしね、ある意味では。ここは【美少女双子姉妹探偵】のデビュー戦として、絡まった状況の糸を解きほぐしてもらえればと」
「えええ……」
「探偵役の人がまさかのサボタージュですか……」
『わたしはそこそこ多才な方だと自負していますが、探偵役まではその範疇に入れていません。その役目にふさわしいのは、この件を謎だと解釈しているお二人の方だと思いますが?』
さわやかに言い切られてしまった。
そこまで言われてしまうと、双子も返す言葉がない。
『繰り返しますが、ここはお二人が自ら答えを導き出すのが良いかと。謎を解くのか解かないのかはお二人の考え方次第。取り組むにしても放っておくにしても、きっと良い勉強になります』
「マネさん意地悪っす」
「既に解決している謎、もしくは謎というほどでもない謎、ということですよね……取り組む意欲があふれ出てくる状況、とは言いがたい……」
口々に不平を鳴らす双子に、マネさんはこう返した。
『詩愛さん心逢さん。お二人が手鞠坂女子学園に入った目的は何でしたか?』
双子はしばし口をつぐんだ。
それから同時にこう言った。
「お母さんたちが昔通ってた学校だから」
さらに詩愛が付け加える。
「お母さんたちが女子高生時代にどんなことしてたのか、自分らぜんぜん知らないんで。お母さんたちの昔のツテとか辿っていろいろ聞いて回ることもできるっすけど……実際に同じ学校で高校三年間を過ごした方が、なにかとあの二人に近づくことができるんじゃないか、って」
「それにお母さんたちを超えたい」
心逢も続いて言いつのる。
「音楽でも小説でも、それ以外のどんな形でも。ほんの少しでもいいからあの人たちに追いついて、ちょっとだけでも追い越したい。あの人たちは本物の天才だったみたいですからね、心逢たちと違って。でもいくら高い壁だからといって、指をくわえて見上げてるばかりなのは性に合いませんから」
『そしてわたしは』
最後にマネさんが総括する。
『お二人のお手伝いをしたい。わたしが尊敬する先生方――白雪静流〈しらゆきしずか〉先生と白雪日向〈しらゆきひなた〉先生の娘さんであるあなた方が、何を考え、どう行動して、何を残すのか。それを自分の目で確かめてみたい』
記録更新、だった。
マネさんの笑顔はまさに破顔一笑で、美少女を自認している双子たちから見ても、文句なしでキレイだった。クール美人な普段の印象とは真逆の、まるであどけない幼子のような。あるいは、露を含んで開いたばかりの色鮮やかな花のような。
『お互いの方針を確認できて何よりです。それではお二方、ご自分たちの目的に沿って、どうぞ手鞠坂での高校生活を楽しんでください。縁の繋がった同窓の生徒たちと交流して、謎に興味があるなら取り組んで、音楽にも小説にも大いに励んでください。……それとちなみにですが』
最後にマネさんはダメ押しの一撃を口にした。
『静流先生も日向先生も、きっとこの程度の謎はご自身で解決できたでしょうね。こちらからは以上です』
――通話が切れた後、双子たちは「ううん……」と唸って考え込んだ。
「なんか上手いこと踊らされてる気がする」
詩愛が言った。
「肝心なことは何も教えてくれない、という雰囲気も強く感じましたね」
心逢も言った。
「とはいえさー。ヒントは色々もらえてる気もするよね」
「ええその通り。少なくともマネさんはこう考えているはずですよね。今回の問題には何かしらの答えがあると」
「それにマネさんは、自分と心逢ちゃんの二人で解決できる問題だ、って思ってる」
「そこまでお膳立てされたら、ねえ?」
「はい。取り組まないわけにはいきませんね。付き合いは決して長くありませんが、心逢たちの扱い方をよく分かってますよねあの人は……さすが、うちの母たちのマネージャーをやってただけはあります」
「それにさァ。この問題を華麗に解決してみせたらさ。また学園新聞とかでチヤホヤしてもらえるんじゃない?」
「しょぼいコンクールの実績じゃなくて、実力を見せつけた上でチヤホヤされるなら……心の中で肩身の狭い思いをする必要もなくなりますね」
「じゃあ、やっちゃう?」
「やっちゃいますかね?」
†
私立手鞠坂女子学園に入学して、一ヶ月と少し。
祭り上げられて背負った肩書きである【双子探偵】は、見栄っ張りでお調子者の本領をこうして発揮し、デビュー戦ともいうべき事件に取り組む運びとなった。
【NOT FOR SALE】
試し読みの無断複製、転売、配布等は禁止します
© 2025 Kurehito Misaki, Daisuke Suzuki / TO Books.
「双子探偵 詩愛&心逢」シリーズのお買い求めはこちらから!

- 双子探偵 詩愛&心逢
- 著:鈴木大輔
イラスト:深崎暮人 - 定価:715円(税込)

- 双子探偵 詩愛&心逢 さようなら、私の可愛くない双子たち
- 著:鈴木大輔
イラスト:深崎暮人 - 定価:715円(税込)