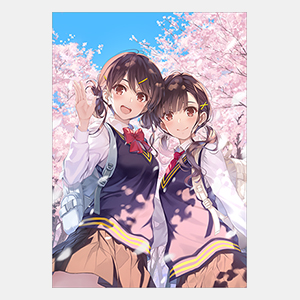- トップページ
- 双子探偵 詩愛&心逢(2/3)
試し読み
双子探偵 詩愛&心逢(2/3)
著:鈴木大輔 イラスト:深崎暮人

「……うわ。入ってるよ手紙」
目安箱を開けた白雪詩愛が目を丸くした。
「ひい、ふう、みい、よ――全部で六通も!」
「ヒマな人たちがいるものですねぇ。この箱が置かれてからまだ一日も経ってないのに」
白雪心逢も呆れ声をあげて、六通の投書に目をやる。
学生寮【叢風館】の廊下。
目安箱、と毛筆で大書されたシンプルなボックスが、双子たちの二人部屋のドア横に設置されていた。そろそろ消灯時間を迎えようとしているこの時刻、廊下には他の寮生の姿はない。
「まあとりあえず……読んでみる?」
「心逢たちに宛てた投書なんでしょうからね、たぶんですけど。まさか捨てるわけにもいかないでしょう。読んでも問題ないのでは?」
部屋に入って投書の中身をあらためてみた。
そのうちの三通はファンレターだった。女子力の高そうな可愛らしい封筒に、これまた可愛らしい便せん。達筆、丸文字、クセのある筆致、で、それぞれ白雪姉妹への想いが記されている。
「うひゃあ。ホントにファンレターだ!」
「ですねえ。本当にファンレターですねえ」
ベッドの端に腰掛けてふたり並び、食い入るように文面を読みふける。
「あ。この人ってコンテストに来てくれてるんだ。道玄坂の会場まで聴きに来てくれたのかなァ」
「こっちの人も。読んでくれてるんですねえ、心逢が小説賞で書いた短編。主催者のウェブサイトに載ってはいるんですけど、けっこうちゃんと探さないと見つけられないコンテンツなんですよね」
「“ふたりとも顔面偏差値が高い”って書いてある」
「“脚がキレイでスタイルがいい”とも書いてありますね」
「“双子探偵が学園を歩いてると、それだけで場の雰囲気が明るくなります”だってさ」
「“見ているだけで目の保養になります、是非お二人で末永く仲良くしてください。でも逆にお二人がケンカしたとしても、それはそれで尊いです”……ちょっと趣味がこじれてる気もしますけど、熱いメッセージではありますね」
うーん、と双子たちは腕を組んだ。
ニヤけ顔を抑えるのに苦労している仕草だ。
「実際どうなん? 心逢ちゃんは最近」
「どう、というと何が?」
「んー例えばさ、自分と心逢ちゃんってクラスは別々じゃん」
「ですね。双子ですし」
「クラスでの心逢ちゃんのポジションって、どんな感じ?」
「相変わらずですよ」
肩をすくめて心逢は答える。
「キラキラした目で見られてます。ちょくちょく話しかけられたりもするんですが――」
「芸能人にでも話しかけるテンションだったりしない?」
「ええまさにそれです。この間は握手を求められました」
「握手したの?」
「しなかったら空気悪くなるじゃないですか。しましたよ握手」
「『キャー! 心逢さんに握手してもらっちゃったー!』『すっごーい! ○○ちゃん勇気あるー!』みたいな反応だったんじゃない?」
「よく知ってるじゃないですか詩愛さん。もしかしてそちらも同じで?」
「うん。似たようなシチュエーションあった。自分の時は『一緒に写真撮ってください!』だったけど」
「撮ってあげたんですか?」
「そりゃね。別に減るもんじゃないし」
「調子に乗ってファンサービスもしてあげたとか?」
「まあねー。肩とか抱いて、顔もかなりくっつけて、ギャルピースして写真撮った。めっちゃキャーキャー言われて気持ちよかった」
「そういうところありますよね、詩愛さんって」
「心逢ちゃんだってファンサしたんでしょ? 斜め四十五度でニッコリ微笑んで、相手の手をわざわざ両手でギュッと握ったりして」
「見てきたかのように言いますね。その通りですよ」
ふう、とふたりでため息。
りんごジュースをグラスに注いで、それぞれの椅子に座る。
二人部屋の主な家具は二段ベッドに二台の勉強机。書棚にクローゼット、さらには小型の冷蔵庫にエアコンもしっかり設置されているから、私物は最小限で済ませられる。ユニットバスに洗面台まで完備されているあたりが寮生に好評だが、調理室や給湯室は共用スペースだ。
「――で。問題はこっちか」
詩愛が残り三通の投書を手に取った。
こちらはファンレターではなく、いわば要望書である。“目安箱”の本来の目的、生徒たちの意見を広く拾い上げるための装置、本来の役割だ。
「うちの学生寮って、学園の生徒なら誰でも出入り自由だからなー」
「学生寮に置いてある目安箱なんですからね、せめて寮生だけが利用できる対象だったらちょっとは楽できそうですが」
「ていうかこういうの、普通は生徒会とかの仕事だと思う」
「学生寮にだって元々あるんですよね、ご意見箱みたいなの。要望でも歎願でもそっちに入れたらいい気もしますけど」
「ま、しょーがないでしょ。自分ら【双子探偵】らしいんで」
「そんなのはですね、しょせんはゴシップ好きな新聞部が勝手に貼ったレッテルじゃないですか。心逢たち別に、華麗な謎解きとかできませんからね? 元々は学生寮で困ってる人をちょっと助けただけの話が、やけに大きくなって広がっただけですし」
「心逢ちゃんが悪いんじゃない? インタビューでドヤ顔しながら語ってたっしょ。『江戸川乱歩の研究となれば、この白雪心逢の右に出る者はいませんね』『探偵という存在は人類が発明したロマンそのもの。憧れがないかと言えば嘘になります。探偵小説とはそもそも――』みたいなこと」
「ドヤ顔で探偵と乱歩を語っていた自覚はありますが、そこまで話を盛ってはいませんよ。乱歩の研究家が世の中にどれだけ居ると思ってるんですか。いくら心逢が調子乗りでも、身の程は知っています。……むしろ詩愛さんの方が悪いんじゃないですか? 『求められたらやりますよ、探偵だろうと何だろうと。期待に応えてナンボなのがロックだと思うんで』とか何とかインタビューで言ってましたよね? 探偵やることがロックになるってどういう理屈ですか。ロックって言っておけばとりあえず何とかなる、みたいなこと思ってません?」
双子はにらみ合った。
すぐやめた。
「そんなことよりこれ。要望書? 的なやつだけどさ」
「なんというか――引っかかる内容ですよねえ」
三通の投書を並べて、詩愛と心逢は首をひねった。
いずれも匿名の投書だ。ある意味では当然といえる。無記名での投函が可能であることが目安箱のいいところだし、素性を明かした上で依頼するなら面と向かって双子のもとを訪れれば済む話だ。
もっとも、面と向かって何かを頼んでくるような相手が学園にいないのも確かである。まだ入学したばかりな上に、詩愛も心逢も妙な形で孤立しているからだ。祭り上げられて遠巻きにされるという、ある意味ポジティブな形で。例外があるとすれば、事あるごとに取材を申し込んでくる新聞部ぐらいのものか。
問題は投書の内容だった。
どの投書も、書かれていることがある意味、ほとんど同じなのである。
「ひとつはこれ」
投書の一枚を詩愛が手に取る。
「字がいちばん上手いやつ。毛筆で書いてるのかな? すごい達筆だよね。時候のあいさつから始まってきちんと結びの言葉も書かれてる。書いてある内容はだいぶ遠回しな言い方してるけど、要するに『生徒会長と寮長の身辺調査をしてほしい』ってことだよね」
「次はこれ」
投書の一枚を心逢が手に取る。
「可愛らしい丸文字ですね。いかにも女子、という感じの。顔文字とか絵文字みたいなのもたくさん入ってて、友達同士でやり取りする手紙みたいなテンションです。半分ぐらいはファンレターみたいな内容ですが――最後に書いてあるのは『新聞部部長と寮長の身辺調査をしてほしい』ということですね」
「最後にこれ」
詩愛と心逢は三枚目の投書を手に取る。
「クセのある文字……上手いんだか下手なんだか」
「芸術点は高いかもしれませんね、ある意味。まあ読めるので問題はありませんが」
「これはもう単刀直入ってやつだ。『生徒会長と新聞部部長の身辺調査をしてほしい』としか書いてないね」
むう。
双子はくちびるをアヒルみたいな形にする。
「頭こんがらがってくる。なんかの謎解きゲームみたい」
「三人の人物が、それぞれ二人の人物について調査の依頼をしているわけですね。登場人物は三人――生徒会長、新聞部部長、寮長。ある種の三すくみみたいな状態なんですかね? じゃんけんのグーチョキパーみたいな」
むむむむ。
双子は眉にしわを寄せて腕組みをする。
「これってどーゆーコト?」
「依頼なんじゃないですか。文字どおりそのまんま」
「いやそれはわかるんだけどさ。入学したばかりの一年生なわけじゃん、自分らって。この学校のこともぜんぜん詳しくないし。そんな自分らにこんな調査させてどうすんの? 身辺調査をしたとして、それでいったい何が出てくるってわけ? しかも調査したとして誰に報告すんの? ぜんぶ匿名で来てる要望書だよね?」
「心逢に聞かれても困ります。まあ【探偵】の仕事ではありますね。心躍るタイプの仕事とは言いがたい、ものすごく地味なやつですが。学園新聞によれば【双子探偵】ってことになっているようですしね、心逢たちって」
「なんだかんだで読んでる人多いってことよね、学園新聞。号外もよく出してるみたいだし、地味に人気あるんだろなァ」
双子は眉間にしわを寄せ、腕を組む。
三通の投書。
三通りの筆跡。
三人の人物への調査依頼。
「よくよく考えるとこれって――ミステリー小説のプロローグっぽいですね。意外にも正統派な感じの。ふむふむ。ほうほう」
「……心逢ちゃーん?」
詩愛が目を細める。
「なんか目の色変わってるけど? もしかして楽しんじゃってる? この状況」
「仕方ないでしょう、ここまでお膳立てされてるんですから。これでもいちおう文芸を志している身です、謎が提示されたら本能的に身体が反応してしまうんですよ。詩愛さんだって、素敵なコード進行が耳に入ってきたら勝手に身体が動き出すクチでしょう? エアギターしたりヘドバンしたり」
「まあそれはそうだけどー」
双子はりんごジュースのグラスに手を伸ばす。
ほとんど同時に手に取ったグラスは、会話が白熱しているうちにだいぶ温くなってしまっている。冷たさを失った糖度の高い果汁は、少しばかり喉ごしが甘ったるい。
「とはいえさー。今回は心逢ちゃんが悪いよね」
「は? 何を唐突に? いきなりひとのせいにしないでくれます?」
「まあまあ。そんなトゲトゲしい声出さなくていいって。今回はたまたま心逢ちゃんがやらかしたけどさ、自分だってもしかしたらそっちの立場に立ってたかもしれないもんね。我ながらどうかとは思うけど、姉妹そろって調子乗りだからなー」
「いやだから。何が?」
「またまたとぼけちゃってー。双子の間で隠し事はなしだよ? ウチらズッ友じゃん? ズッ姉妹じゃん?」
「とぼける、の意味がわからないと言ってるんですよ。言いたいことがあるならもっと具体的にどうぞ」
「だって心逢ちゃんでしょ? 目安箱を作って置いたの」
「…………」
心逢は何とも言えない顔をした。虚を突かれたような、そして唐突に状況の本質を理解したかのような。
生まれてこのかた十五年の付き合いである。妹のその顔だけで、詩愛は察した。
「え、マジで? 心逢ちゃんじゃないの?」
「心逢なわけないじゃないですか。お調子者の自覚はありますが、こんな馬鹿げたものを自分で設置しない程度の分別もあります」
「じゃあ誰が置いたの? この目安箱」
「もちろん詩愛さんでしょう。姉の酔狂もここまで来ると度しがたいですね、と思ってはいたんですが、口には出しませんでしたよ。双子の情けで」
「いやいや。自分だって作ってないよ、こんな面倒くさいモノ。そもそもいつ作ったっていうわけ? 今もこうやって同じ部屋で寮生活してるし、学校でもほとんど一緒に行動してるし。こんな夏休みの工作みたいな箱を作ってる場面なんて、お互いに見たことないでしょ?」
「それを言ったら目安箱を部屋の前に置く隙なんて、心逢たちにはお互いになかったことになるじゃないですか。……というか詩愛さん、勝手に開けて中身を見たんですか? 自分が置いた目安箱でもないのに?」
「いやだって、心逢ちゃんが置いたものだとばかり思ってたからさ」
「自分が置いた目安箱でもないのに、新聞部にはドヤ顔でインタビューに答えてたんですか? 『学園の人たちの役に立てるなら嬉しい』とか言って」
「それ言ったら心逢ちゃんだって同じじゃん。『微力を尽くします』とかなんとか、優等生な受け答えしちゃってさ」
「詩愛さんのドヤ顔の方がひどかったです」
「心逢ちゃんのドヤ顔の方が見てらんなかったね」
双子はにらみ合った。
すぐやめた。
三通の投書。
三通りの筆跡。
三人の人物への調査依頼。
そこに加えて、誰が置いたのかもわからない目安箱の謎。
「さすがにちょっと」詩愛が言った。「放置しておけない状況になってる気がする」
「奇妙な雰囲気はありますよね」心逢も言った。「誰が何の目的でやってるのかは知りませんが、恣意的なものは感じます」
さてしかし、どうしたものだろう?
祭り上げられた結果、【美少女双子姉妹探偵】ということになぜかなっているが、言うまでもなく詩愛も心逢も素人である。ちょっとギターが弾けて、ちょっと小説が書けて、ちょっと顔がいいだけの高校生だ。身辺調査だけなら手間を掛ければ済む。だがその後はどうなる? 目安箱に入っている投書に応えて、いわば便利屋みたいに使われつつ、学園でもっとも注目される存在として下にも置かない扱いをされる。ただし、周囲からのいささか一方的な期待に応えるために、柄にもない役割を演じ続けることになるかもしれない。もしかすると高校生活三年間ずっと。
「それはちょっと……ねえ?」
「ええさすがに。あまり想像したくない未来ですよね」
「なんかこう、気持ちいいんだけど気持ち悪いっていうか」
「アイドル扱いされるのはいいんですけどね、承認欲求満たされますし。ですがちょっと窮屈すぎますか、今のポジションは」
「なかなか難しいミッションだよ……チヤホヤされるのは嬉しいからできるだけ今の状態はキープしたい。でも祭り上げられすぎるのは嬉しくない」
「謎も解決したいですよ。心逢たちに何かが起きているのは確かなようですし。見て見ぬふりをして放っておくのは性に合いません」
「誰かに聞いてみる? クラスの人たちとか、先生とか。保健の先生とか」
「どうでしょうねえ……それはそれで白旗を揚げてるみたいで気が進みませんね。心逢たちの目的にもそぐわないかと思います」
「そうねー、それもあるかァ……それにしても急に色んなことが起きるよね。田舎に住んでた時はもっと静かで何も起きなかった気がするけど」
「東京って変なところですよね」
「いやいや。自分らも昔は東京に住んでましたからー」
心逢のボケに適当な突っ込みを入れておいてから、詩愛はあらたまって、
「じゃあどうする? とりあえず動けるだけ動いてみる?」
「微妙なところですね。心逢たちにはお調子者の自覚はありますが、自分の能力の程度も理解しているつもりです。その理解が心逢に告げています……『あなたたちだけで解決しようとするのは効率が悪いですよ』と」
「なんかカッコイイ風の言い回ししてるけど、まあまあダサいこと言ってる気がする」
「詩愛さんは自分で何とかできる見込みがあるんですか?」
「いや。ぜんぜんないね」
となれば誰かに頼ることになるだろう。
そして詩愛と心逢にはこういう時、頼りにできそうな相手はひとりしか候補が思い浮かばなかった。
【NOT FOR SALE】
試し読みの無断複製、転売、配布等は禁止します
© 2025 Kurehito Misaki, Daisuke Suzuki / TO Books.
「双子探偵 詩愛&心逢」シリーズのお買い求めはこちらから!

- 双子探偵 詩愛&心逢
- 著:鈴木大輔
イラスト:深崎暮人 - 定価:715円(税込)

- 双子探偵 詩愛&心逢 さようなら、私の可愛くない双子たち
- 著:鈴木大輔
イラスト:深崎暮人 - 定価:715円(税込)