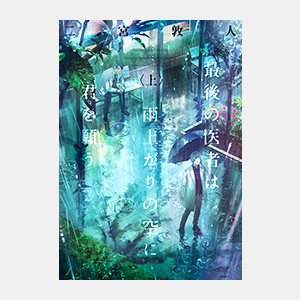- トップページ
- 最後の医者は桜を見上げて君を想う(2/5)
試し読み
最後の医者は桜を見上げて君を想う(2/5)
著:二宮敦人
「マジすか? 浜さん、白血病? あれって癌なんですよね?」
電話の向こうで、部下の堂島が素っ頓狂な声を上げた。
「ああ……血液の癌だって、医者は言ってた」
総合病院の一階待合ホールは広い。行きかう人の数も多く、騒がしい。浜山は受話器をもう少し耳に近づける。
「ですよね。ドラマで見ましたもん。でも、こんなに急になるもんなんですか?」
「俺の場合、急性骨髄性白血病と言って、進行が速いらしい。それも癌細胞が骨髄の中から溢れ出して、既に全身に回っている状態だそうだ……」
浜山は自分で言いながら、寒気を感じた。
俺の骨の中心部には、異常な細胞がたっぷり詰まっているのだ。奴らは増殖し、正常な細胞を圧迫して、どんどん減らしている。それに飽き足らず、骨髄から血流に乗って流れ出し、体中を蠢いている。俺の腹にも、足にも、指先にも。
想像すると不気味で仕方なかった。
「わかりました。例のプレゼンは任せといてください。こっちでうまくやりますから」
「え?」
「だって入院になりますよね?」
「あ、ああ。そう言われた。すまない……急な連絡で」
「何言ってんですか、浜さん。白血病ですよ。会社の心配してる場合じゃありません。大丈夫です。浜さんいなくたって平気ですよ、自分や西尾で回します。入院は、クリーンルームですか?」
「いや、しばらくは一般病棟だそうだ」
「ならお見舞いにも行けますね。落ち着いたら受注の報告をお土産に、チームのみんなで行きますから。闘病頑張ってください。では」
「ああ。ありがとう」
電話は切れた。緑色の公衆電話に受話器を戻して、浜山はふうと息を吐いた。
俺がいなくても大丈夫か。堂島は元気づけようとして言ったのだろうが、逆に悲しい。
しかしあいつ、よく知ってたな。テレビドラマで見たんだろうか。白血病の罹患率は年間で十万人あたり六・三人だと聞いた。確率は〇・〇〇六三パーセント。俺だって、ドラマの世界の病気だと思ってたよ。
横の公衆電話では老婆がにこにこしながら誰かと話していた。迎えを呼んでいるらしい。帰ったら寿司が食べたいなどと言っている。
少し落ち着いて考えたい気分だった。
気合いを入れて締めてきたネクタイを緩める。
浜山はプレゼン資料の入った鞄を持ち、ゆっくりとソファまで歩くと、深く腰かけた。ソファは四人掛けのものが無数に並んでいる。会計や案内を待つ患者が座り、週刊誌を読んだり、壁にかけられた大きなテレビを茫然と眺めていた。
腕を骨折している人がいる。マスクをして咳をしている人もいる。子供を連れた母親がいる、眼帯を付けた若者がいる。彼らは束の間病院に訪れ、診察を受けてはすぐに外へと帰っていく。
俺だってそのつもりだった。
少し肩の付け根が痛くて、体がだるく、たまに息切れがあった。ちょっとした体調不良。休日出勤と残業が続いているから、仕方がないことだと思っていた。症状は治ったり、ぶり返したりしながら、ついに昨日は熱が出た。妻にお尻を叩かれ、病院で薬だけ貰おうと思ってやってきた……。
なのに、なぜ。
なぜ俺が。
もらった処方箋を片手に、腕時計を見ながら外に出て行くOL風の女性がいる。自動ドアが開き、女性を送り出してまた閉じた。
俺は仕事に行かない。行かなくていいんだ。こんな真昼間から、テレビを見ている。明日も明後日も、一か月も二か月も。
途方に暮れそうだった。小学校の時、休校日に間違って来てしまったような、そんな心細さを思い出す。世の中が自分を無視して動いているようだ。
鞄の中の名刺入れが、弁当が、手帳が、悲しかった。
浜山は鞄を開き、資料を取り出した。プレゼンに備えて昨日何度も読み込んだそれは、赤で無数の書き込みが加えられ、折れ目が付いてぼろぼろになっている。意味もなく資料に目を落とす。無意味だと知っていながら、ページをめくる。
とにかく時間が欲しかった。静かに考えたい気分だった。
仕事の関係者には連絡を入れた。問題は妻だ。
妊娠六か月の妻にどう伝えればいいのか。
もう少し考えなければ、とても思いつきそうになかった。
「白血病の治療方針は『トータル・セル・キル』というものです」
主治医の赤園は黒縁眼鏡の奥で目をしばたたかせながら、のそりと立ち上がる。そしてホワイトボードに細胞の絵をいくつか描き、その上に大きく×印を付けた。
「つまり血中の細胞を全滅させるということです。正常細胞も、異常細胞も」
「ぜ、全滅ですって……」
「浜山さんの癌細胞は今、自由に血の中を泳ぎまわっています。細かい癌細胞を一つ一つ選別してやっつけることはできません。そして癌細胞は一つでも撃ち漏らせば再び増殖してしまいます。ですから犠牲は覚悟の上で、強力な抗がん剤を投与します。正常細胞もろとも根こそぎ死滅させるのです。癌細胞がいなくなるまで」
赤園は淡々と、説明を行う。その声がぼそぼそと無機質な面談室に響き渡る。浜山は震えながら聞いた。
「そんなことをしたら、俺の血はなくなってしまうんじゃありませんか」
「なくなりはしませんが、血球の数は激減します。なのでその分を輸血などで補わなくてはなりません。また、一時的にばい菌への抵抗力が失われてしまいます」
「どうなるんですか」
「普通ならちょっとした風邪ですむような病気も、命にかかわる症状になってしまうんです。ですから衛生には十分気をつけましょう。食事前、トイレ後のうがい、手洗いは欠かさずに。何かに触れたら必ず手を消毒。血球数が一定量を切ったら、無菌室という特別に隔離したお部屋に移っていただくこともあります」
「クリーンルームってやつですか」
「あ、ご存知でしたか。まさにそれです。ただ、無菌室では面会はご家族のみ、一日一時間までとさせていただいてますので、ご了承ください」
「……はい……」
「さて、処方するお薬ですが。抗がん剤はアンソラサイクリン系という、まあ実績のあるお薬ですね……それから場合によっては利尿剤と強心剤、輸血は血小板を……」
赤園は薬について説明し、一通り話し終わるとこちらを見た。
「何かご質問はありますか?」
浜山は口ごもる。口の中がカラカラだった。
「あの……」
言ったところで咳が出た。それを見て察したように、赤園が口を開く。
「ああ、副作用について説明をしていませんでしたね。抗がん剤は強いお薬ですので、やはり副作用があります。聞いたことがあるかもしれませんが……まずは脱毛。それから口内炎、吐き気、下痢などです。しんどいかもしれませんが……浜山さんが苦しんだ分だけ、癌もやっつけているわけなので、頑張っていきましょう。私も吐き気止めなど処方して、サポートしますので」
「いえ、あの」
「はい?」
浜山はもう一度咳をし、そしておそるおそる聞いた。
「あの……治るんですよね」
赤園は虚を突かれたような表情をする。
「治るんですよね。その、トータル・セル・キルですか……それをやれば、治るんですよね。俺、死なないですよね」
赤園は笑った。
「あ、ええと、基本的に治ります。言ったじゃないですか。白血病は、今は治る病気なんです。完治した人だっていっぱいいますよ」
浜山も釣られて笑う。それを見てか、赤園は口を滑らせた。
「ほとんどの人が、このやり方で寛解まで持ち込めていますからね」
「ほとんどの人……?」
浜山の口端が引きつった。
「ほとんどって、どれくらいですか」
赤園が口を閉じ、一瞬だけ無表情になった。その眼鏡の奥の目が、浜山をぼんやりと見る。それから再び笑みを浮かべ、言った。
「ええと、約八十パーセントです」
五人に四人。
浜山は、冷たく静かに背中に汗が流れるのを感じた。
五人に四人。五回に四度。それは、果たしてくぐり抜けられる確率だろうか。血液内科の大部屋、ベッドに寝転んで浜山は天井を見つめていた。扉が開き、点滴棒を引きながら痩せた老人が室内に入ってくる。
先ほど軽く雑談した仲なので、浜山は会釈した。彼もまた、急性骨髄性白血病だと言っていた。
老人は大きな息を吐き、いかにも億劫そうに自分のベッドに身を横たえた。
この大部屋には六人の患者がいる。つまり、この部屋で一人は治らないのだ。治らなかったらどうなるんだ? 治らないって、どういうことだ? それってつまり、死……。
恐ろしくて、赤園に確認することはできなかった。
ふと、入口に不安そうな顔が見えた。細面の女性が首を伸ばして覗き込み、病室の中を窺っている。
「おう」
浜山は手を振った。
取るものも取りあえず駆けつけてきたのだろう、髪がぼさぼさの女性は浜山を見てほっと息をつくと、垂れた目を細めて弱々しく笑った。浜山も、同じように笑った。
女性は大きく膨らんだ腹を抱えるようにしてベッドサイドの椅子に腰かける。浜山はカーテンを引き、口元を緩めて妻の腹に触れた。
「京子。悪いけどスーツ、持って帰ってくれるか」
浜山はつとめて明るい声で言い、脇のハンガーにかけたスーツと、朝に着て昼脱いだばかりのワイシャツを示す。京子は大人しく頷いた。
「しばらく着ないからな。クリーニング、しといてくれ。退院する頃には秋だ。いや、その腹じゃ持って帰るのは大変か。じゃあ郵送するから受け取りを頼む」
「ねえ、雄吾。そんなことより、あなた……」
「ん? そうだ、次の健診はいつだっけか」
「健診は来週」
「そっかそっか。次こそ一緒に行こうと思ってたんだけど、悪いな。行けなくなっちまった。エコーだっけ? あれで見るの、楽しみにしてたんだけどなあ」
「……」
京子は眉じりを下げて浜山を見つめていた。その悲痛な表情を見て、浜山は反射的に笑顔を作る。
「どうした? そんな顔すんな、大丈夫だよ。それより治療費だよな、保険にでも入っておけば良かったな、まさかこんな病気想像もしてなかったし」
「雄吾……」
「なんだよ、電話で言ったろ? 今は治る病気なんだって、センセイが言ってくれたんだ。心配すんなよ」
京子は浜山の言葉には答えなかった。ただ、まばたきもせずに浜山を見上げ、その人差し指をすっと差し出して頬に触れた。
「あ……」
冷たかった。いや、温かかった。その不思議な感触で、ようやく気づいた。
「俺……泣いて……」
慌てて俯き、病院服で目を拭う。音もなく流れていた涙が、裾を染める。手が震えていた。唇がかじかんでいた。歯の奥が、かちかちと鳴っていた。
背後から温もりが覆いかぶさってくる。京子だった。京子が、俺を抱いてくれている。
「一番怖がってるの、あんたの癖に。強がらなくていいの」
「……うるさいな」
くそ。こいつには敵わない。
「わかるよ。驚いちゃったんだよね。今日までずっと、普通に過ごしてきたのに……急にこんなことになって、入院なんて、びっくりしちゃったんだよね。雄吾って、そういう人だもん」
ぽん、ぽん。ゆっくりと一定のリズムで、京子が背中を優しく叩いてくれる。それは不思議と心を落ち着かせた。叩かれるたびに、そのたびに、悪いものが体から消え去っていくような気がした。
「……だってよ。プレゼン……俺……」
声がまともに出ない。
浜山はまるで子供のように嗚咽していた。
「わかってる。頑張ってたもんね。ずっと前から、毎日遅くまで準備してたの、知ってる。私は、知ってる」
京子はゆっくり浜山に合わせて言う。浜山はしゃくりあげながら、歪む視界を睨み付けながら、必死で言葉を紡ぐ。ぽたぽたと熱い涙がベッドに落ちた。
「……それに、俺……」
「ん?」
「俺ッ……お前に子供……のに、こんな……してる場合じゃ……」
「大丈夫。全部、大丈夫」
京子は四つも年下の癖に、こういう時は不思議に頼もしい。これが母性なのだろうか。寄り掛かればそのままどこまでも受け止めてくれそうな、温かさと優しさ。それに比べて俺は何て頼りないんだ。子供が、来年生まれてくるというのに。
男の子だって、つい二日前にわかった。
昨日から、名前を考え始めた。
そして今日、俺は……。
「焦らないよ。大丈夫だよ。雄吾、一人じゃない。私がいるよ」
「だけど、俺……」
顔がくしゃくしゃになっているのが自分でわかった。自分でも正視に耐えないだろう顔を、京子が掴んで持ち上げる。そして正面から見つめ合う。
「一緒に頑張ろう。ね、今までだってそうやってきたじゃない。あなたが事故を起こした時も、私が鬱になった時も。ね、何とかなって来たじゃない」
京子の大きな黒い瞳の中で、自分がまばたきしている。
「一緒に治そう。二人なら、大丈夫。ね。一人で抱えないで、何でも相談してね」
京子がにっこりと笑う。その唇が、震えるほど愛しく思えた。
感染症には気をつけろと言われていた。肉体的接触はできるだけ避けるようにと言われていた。だから浜山は指を伸ばした。
京子の唇に指で触れる。京子は逃げようともせず、それを受け入れた。触れ、撫で続けている間、唇はずっとそこにいた。なぜか出会ったばかりの頃を思い出す。
体の震えが、少しだけ治まった。
【NOT FOR SALE】
試し読みの無断複製、転売、配布等は禁止します
©Atsuto Ninomiya / TO Books.
「最後の医者」シリーズのお買い求めはこちらから!

- 最後の医者は桜を見上げて君を想う
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(上)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:638円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(下)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:594円(税込)

- 最後の医者は海を望んで君と生きる
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)