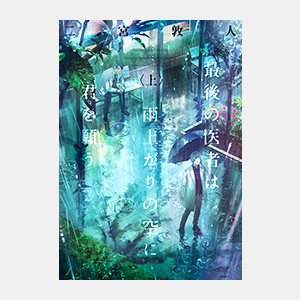- トップページ
- 最後の医者は桜を見上げて君を想う(3/5)
試し読み
最後の医者は桜を見上げて君を想う(3/5)
著:二宮敦人
八月十三日
「福あら、福原先生、お、おりあ……お願い、あり、あるんだ」
回診中、小学二年生の澤田ハジメが、何度も言い直しながら福原に声をかけた。福原は聴診器を首に戻してから優しく笑う。
「ん? 何だい、言ってごらん」
「あ、あのさ。つ、ふる、いや、さるが」
澤田は脳腫瘍を患っている。夏休みだというのにどこへも遊びに行けず、ベッドの上で毎日を過ごしていた。シーツの上に散らばったロボットの玩具や、擦り切れた漫画本がいじらしい。
「ふる……?」
「あ、いや。つ、鶴」
澤田の言葉はたどたどしい。脳腫瘍による言語障害だ。福原はできるだけ澤田を緊張させないよう、あえてテンポを落として会話した。
「ああ、千羽鶴か。学校の友達にもらったのかい」
澤田が掲げた鶴の束を見て福原は笑った。色とりどりの折り紙で作られた鶴。澤田も歯を見せて微笑む。いくつかの歯が抜け、永久歯になりかわりつつあった。
「で、でも俺。味噌する。濡らして……ほら」
「ああ。味噌汁をこぼしちゃったのか」
鶴の束が一つ、ふやけてぼろぼろになっていた。いくつかは破れている。澤田は申し訳なさそうに折り紙の束を取り出した。その紙は折りたたまれ、ひし形を成している。
「これは? 作り途中の折り紙かい」
「うん。俺、こら、こわした分、作りたうて……。で、折った。だけど、ここが折れないくて、福原先生に、そこだけ、わるいけど」
「ああ……」
福原は一枚の折り紙を手に取った。確かにこれは鶴だ。途中までの鶴だ。手にも麻痺が出ている澤田は、さぞ苦労してここまで折ったのだろう。何本も重なり、歪んだ折り目がそれを示していた。
羽を広げることができず、縮こまったままの鶴はどこか澤田と似ていて、福原は胸が締め付けられる思いがした。
「ごめん、先生。忙しいおね……。俺、これ、シジュツ前に、作りたい、だ」
おずおずと言う澤田。その手から折り紙を取り、福原は明るく声をかけた。
「この折り紙、貰っていいかな」
「え?」
「お医者さんと看護師さんで、足りない分を作ろう。自分で作るより、俺たちの想いを込めた方が、ずっと効くはずだ、そうだろ?」
澤田が目を丸くした。
「福あら、福原先生。いいの?」
「もちろん。手術は明後日だよな。それまでに間に合わせるよ」
「……先生。シュジツ。痛い、だよね。俺……」
澤田が顔を青くして俯く。福原はその大きな掌を広げ、体格の割に細く長い指で澤田の頭を撫でた。
「大丈夫だ」
「先生」
「手術は、俺がやる。俺は絶対失敗しない」
「……ほんとう?」
「嘘なんかつかないよ」
「俺……まら、ドッジできる?」
「できる。ドッジボールだって、サッカーだってできる」
「だって……もう、おりあ、折り紙も、掴めないのに……」
「掴めるようにしてあげる。だけど先生一人じゃだめなんだ。ハジメ、一緒にやろう。ハジメが手術とリハビリを諦めずに頑張ってくれたら、先生は絶対君を治してあげる。この手に誓って、約束するよ」
福原は澤田の肩を抱き、目線を同じ高さにしてまっすぐに見た。澤田はその澄んだ瞳を覗き込む。テレビに映るヒーローのような、燃えるような瞳だった。
澤田は顔を歪ませた。唇が震える。怖いのだろう、無理もない。
発症してからどんどん麻痺していく体。止まらない嘔吐、頭痛。親や友達からも離れて一人入院し、明後日には頭にメスを入れて腫瘍を切り取るのだ。八歳の彼には大き過ぎる試練だ。
それでも、澤田は恐怖を飲みこんだ。
涙も弱音も全部こらえて、福原に言った。
「約束、ふるよ。シジュツと、リハビリ……頑張るよ。だから……だから先生……」
後は言葉にならない。福原は頷く。そして、澤田の痩せた背をぱんと叩いた。
「男と男の約束だ」
澤田も潤んだ目で頷いた。福原は折り紙を持って立ち上がる。
「これ、貰ってくぞ。手術前には、千羽揃った姿で返すから」
澤田は健気に微笑んでみせた。福原はそれを見届けると、澤田の病室を出た。次の病室へと歩く。その胸の奥は火が宿ったように熱かった。
──約束するまでもない。必ず助けてやる。俺は、絶対に諦めない。
病室に入る前に、福原は看護師に千羽鶴と折り紙を預けた。
「これ、みんなで折るように伝えておいてくれないか」
「わかりました」
「明日までだ。それから俺も一枚折るから、一つ残しておいてくれ」
「はい、先生」
看護師は頷くと、千羽鶴を持って医局の方へと向かった。
暑い。
内科医、音山晴夫は太り気味の腹を揺らしながら、汗を拭き拭き歩いていた。ただでさえ丸顔なのに、軽く汗を含んだ髪が輪郭に沿ってしな垂れており、その頭は満月のように綺麗な円形に見えた。肌の血色は良く、頬などは赤く染まっている。
二階の端っこまでやってきたところでふうと息を吐き、もう一度額の汗を拭いた。それから院内図を見る。
おかしいな。このあたりのはずなんだが。
皮膚科のさらに奥。健診センターすら通り過ぎた。一向にそれらしきものは見えてこない。もうこの先には職員用の手洗いしか……。
「まさかあれか」
先日まで予備倉庫だったはずの扉に、「第二医局」と張り紙がある。音山は眉をひそめた。張り紙はごく普通のコピー紙、文字はマジックで手書き。
ずいぶんな扱いじゃないか。
音山は丸い目で念のためにあたりを見回してから、扉をノックした。
第二医局。
人員が増えたため、医局が一室では手狭になったので急きょ用意された部屋。と言えば聞こえはいいが、実質はある一人の問題医師を隔離するために作られた場所に過ぎない。
「おーい、いるかい。入るよ」
音山は扉を開く。半ばまでは開いたがすぐにつっかえた。目を白黒させていると、中から声がした。
「そこまでしか開かないよ。何とか滑り込んでくれ」
桐子修司だった。音山は呆れながらも、脂肪で分厚い体をゆすって、なんとか扉の隙間から室内に入り込んだ。
「凄い部屋だな」
部屋には窓がなく、明かりは小さな電球一つ。ひどく息苦しく感じる。部屋そのものが小さいためでもあったが、最大の原因は所狭しと積み上げられた医療品の段ボールだ。生理食塩水にガーゼ、包帯……。段ボールは部屋の半分を占め、扉を全開することすら妨げている。
「何もこんなところに置かなくても」
「音山、仕方ないんだよ。ついこないだまで倉庫だったんだから」
桐子は白衣を身にまとい、段ボールの一つを机に、別の一つを椅子にして弁当を食っていた。不機嫌そうな顔だったが、それが彼の普段の表情であることを長い付き合いで音山は知っていた。
「こないだまでどころか、今だって倉庫だよ。君は第二医局に異動になったわけじゃない。倉庫で仕事させられているだけだ」
「的確な表現ですね」
くすくす、と笑い声がした。音山が振り返ると、クリップボードを持った長身の看護師が立っていた。神宮寺千香だ。切れ長の目にぷっくりした唇。ストレートの黒髪を後ろでまとめているが、数本が横向きに飛び出している。それはだらしなさと色気との狭間で、独特の魅力を放っていた。
「別に倉庫だって構わないよ。どこで仕事をしようが変わりはない。むしろ個室の方が僕は過ごしやすくていい」
桐子は平気な顔でそう言い、走り書きのメモを神宮寺に渡す。神宮寺はそれを笑顔で受け取るとクリップボードに挟んだ。能天気な二人に我慢がならず、音山は言う。
「わかってるのかい。これは明らかに嫌がらせだよ。副院長が画策しているんだ」
「副院長? 福原が?」
「そうさ。福原は自分の権力を使ってやりたい放題だ。そもそも君が皮膚科に追いやられたことからして変だったじゃないか。君はずっと内科系を希望していたのに、無理やりだ。あんな人事、普通だったらあり得ない」
「人が足りないと言うんだから仕方ないじゃないか。それに皮膚科だってやりがいはあるし、素敵なところだよ」
「素敵だって? 例えばどこが」
「そうだね、急患が少ないとか……」
音山は顔を手で覆った。
「桐子、君は呑気だなあ。いいかい、福原は君に最後のチャンスを与えたつもりでいるんだよ。これで反省することなく、引き続き問題を起こすなら、君……病院を追い出されてしまうよ」
「そうなの?」
「そうだよ。同期のよしみで忠告に来ているんだから、よく覚えておいてくれよ」
「そうだったのか、ふーん……飲むかい?」
桐子が魔法瓶を手に音山を見る。
「コーヒーか」
「いや。お湯だけど」
「……いらないよ」
「そう。僕は飲むよ」
魔法瓶から白湯を注ぐ。柔らかな蒸気が立ち上った。桐子はそれをうまそうにすする。副院長室にはデロンギのコーヒーメーカーが置かれているのに比べると、何という落差だろう。
「ちょっと……桐子。それ、何だい」
「え?」
「それだよ、それ。箸代わりにしてるもの」
「ああ。ボールペンだけど」
桐子はそれが何か、と言いたげな顔で、黙々と弁当の中身を二本のボールペンで口に運んでいた。
「相変わらずだな、君は……」
「洗えば問題ないだろう。要は必要な機能を満たすかどうかなわけで」
桐子は電子カルテを眺め、またメモを取る。音山は苦笑する。大学の頃からこういう奴だった。鞄代わりにビニール袋に教科書を入れていたこともあったっけ。
「まあいいや、俺もちょっと飯を食わせてもらうよ」
「どうぞ」
音山は売店で買ってきたサンドイッチの包装を取り、口をあんぐりと開いて深めに差し込んだ。もすもすと中に押し込みながら、手にしていたクリアファイルから一枚の折り紙を取り出して広げる。桐子が訝しんだ。
「……何してるの?」
「え? 折り紙だよ。鶴を折ってるんだ。そうだ桐子、お前も一枚折れよ」
「何のために」
「福原が脳腫瘍の患者さんと約束したんだってさ。千羽鶴を完成させて、手術を成功させるって」
桐子は音山から一枚の折り紙を渡されると、不思議そうにそれを眺めた。
「どうして人は、こういうものに頼るのかな」
「え?」
「千羽鶴で腫瘍が消えるなら誰も苦労しない。これまで何羽の鶴が病院に届けられ、そして虚しく燃えるゴミになっていったんだろうか」
「桐子。みんな、千羽鶴が病気を治すと考えてるわけじゃない。だけど人はそれで元気づけられるんだ。病気と戦う人のために、人は何かをしたいんだよ」
「何かをしたいというなら、医療費の足しにと現金を渡すのが一番いいと思うけどね。鶴を折るのは自由だけど……鶴を折るだけで、何かをしたつもりになってしまうのは良くないよ」
音山は桐子の顔を覗き込む。彼は無表情だった。
「僕たちだって、鶴を折るよりは一人でも多くの患者さんを診た方がいいはずさ。そうだ、これからは不要な鶴を捨てなければいいんじゃないか? 死んだ患者の鶴は取っておいて、また別の患者に使えばいい。紙の無駄も減る」
桐子は平然と言ってのけた。冗談という雰囲気ではない。完全に本気だった。神宮寺がふふっと笑った。
「桐子先生、それを他の人の前で言ったら空気が凍りますよ」
「そうかい?」
音山がため息をついた。
「桐子、君は本当、相変わらずだなあ……」
他人の感情に鈍感というか。
「音山先生も、よく桐子先生と友達やっていられますね」
「もう慣れたよ」
桐子はしばしば人をぎょっとさせるようなことを言うが、悪意があって発言しているわけではないのだ。彼なりに真剣に考えているのだが、結果としてピントの外れた答えを出す。
「僕は正論を言っているつもりなんだけど」
「正論だけでは通用しないのが病院だよ。だから君は、こんなところに押し込められるんだ」
「そうなんだ」
桐子はきょとんとしている。
彼は自分の言葉に棘が含まれていても気づかない。張り切って美容院に行ってきた女性に「その髪型は前より不細工に見えるね」と言い放ち、一発で恋を終わらせたのは同期の間では有名な話だった。
ただ、他人の嫌がらせにも無頓着だ。「個室の方が過ごしやすくていい」との言葉は、本心からなのだろう。喜んでいる節さえある。
ふと、桐子が開いているノートパソコンの画面が音山の目に入った。
「ちょっと待て。桐子、何を見ているんだ、それ」
そこには電子カルテが表示されている。
「それ、どこの患者だ。君の受け持ちじゃないだろう」
「血液内科だよ」
音山は身を乗り出した。
「……またか。死神じみた嗅覚だな」
「まあね。カルテを読みこむのは好きなんだ」
皮肉のつもりだったんだが。音山は心の中でこぼす。
背後から覗き見るだけでわかる。先ほどから桐子がカルテを眺め、メモ帳にピックアップしている患者たち。それはみな死病の患者ばかりだ。もはや手の施しようがない病気。死が目の前にまで迫っている、あるいはそれに近い状態。医学を学んだ者なら流し読みするだけで見当がつく。あるのだ。死臭が漂い、死相が現れ、禿鷹があたりを飛んでいるカルテというものが。
思わず目を背けたくなるような、死の気配の濃いカルテを桐子は黙々と読みこんでいる。
「……桐子。するのか。その患者の面談」
「患者さんから依頼されればね」
「そうやってよその患者に首を突っ込むから、問題が起きてるんだぞ。わかってるよな。これ以上、福原を怒らせたら……」
「どうして福原の顔色を窺わなくちゃならないんだい。僕ら医者が向き合っているのは、患者だけだよ」
音山は歯噛みした。
桐子、君は陰で何と呼ばれているのか知っているのか。それがどれだけ医者として恥ずべき仇名なのか気づいているのか。
人を死に追いやる医者。
──死神。
【NOT FOR SALE】
試し読みの無断複製、転売、配布等は禁止します
©Atsuto Ninomiya / TO Books.
「最後の医者」シリーズのお買い求めはこちらから!

- 最後の医者は桜を見上げて君を想う
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(上)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:638円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(下)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:594円(税込)

- 最後の医者は海を望んで君と生きる
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)