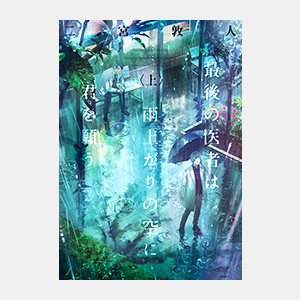- トップページ
- 最後の医者は桜を見上げて君を想う(4/5)
試し読み
最後の医者は桜を見上げて君を想う(4/5)
著:二宮敦人
八月十九日
京子は箪笥を開ける。そしてワイシャツを数えようとしている自分に気づき、ため息をついた。
結婚してからずっと続けてきた習慣は、そう簡単に抜けはしない。あの人は家にいないのに、会社になど行かないのに、ワイシャツも、ネクタイも、靴下も、準備してしまう。
人が一人家からいなくなるというのは、思っていた以上に大きな変化だった。
作り過ぎた料理をタッパーに仕舞う虚しさ。お風呂を出る時、保温機能をオフにする寂しさ。一人分、布団を敷かない味気なさ。
何気なく行っていた作業の全てに、雄吾との繋がりという背景があったと気づかされる。
ついこの間まで、一緒にいたのに。
食後、私のお腹に触れながら、家族が増えたらもっと広い家に引っ越そうか、なんて話していたのに。この喪失感の前では、何もかもまるで夢のようだ。
時々恐ろしくなる。
このまま雄吾が帰って来なかったら、そんな思いが頭をかすめる。
雄吾がいない毎日に慣れることで、本当に雄吾がいなくなってしまうような気もした。だったら慣れたくなんかない。辛い思いを抱えていたい。
お腹がぽこんと動いた。中の人間が、京子を内側から叩いている。
京子はソファに座り、自ら腹を撫でた。
そうだよね。頑張らなきゃ。お母さん、頑張らなきゃね。
雄吾だって、頑張ってるんだ……。
抗がん剤の投与を目の前で見た時を思い出す。
透明な袋に入れられた鮮やかなオレンジ色の液体が、点滴棒で中空に吊り上げられている。それがぽたぽたと落ち、かすかにチューブを震わせながら雄吾の体の中に染みこんでいく。
まるで清涼飲料水のような液は、血管の隅々にまで行きわたり、血中の細胞を破壊し尽くすのだ。雄吾の顔で、手で、胸で、腹で、足で、その皮膚の一枚下で彼の細胞が死んでいく。
あの時、雄吾は何も言わなかった。
ただ目をかっと開いて、オレンジの液体が自分を目がけて突き進むのを、見つめていた。
六時。病院では今頃、食事の時間だろう。何を食べているだろうか。一人で寂しくないだろうか。遠くにいる雄吾を思い、京子は夕焼け空を見上げた。
浜山は小さなカツを箸で掴み、齧った。
肉か魚だと思ったら、それは野菜だった。中にチーズが入っている。これ面白いね、と言おうと思って顔を上げる。
正面には誰もいない。ただテレビのバラエティ番組が無音で流れているだけ。いつもそこに座っていて、から揚げを半分こしたり、醤油やソースを渡し合いながら一緒に食事をした妻の姿は、どこにもない。
ため息をつく。涙がこぼれそうにすらなった。誰とも知らぬ配ぜん係が運んでくる病院食は、色々と工夫されているのはわかったが、ひどく味気なかった。
たった一人の食事。たった一人の就寝。
一人暮らしをしていた頃には平気だったあれこれが、今はひどく胸を締め付ける。
ふと、味噌汁の上にはらりと何かが落ちた。浜山はじっとそれを見る。髪の毛だった。おそるおそる頭に手をやり、軽く引っ掻いてみる。ぱさぱさと音を立てて、まるで埃でも払ったかのように頭髪が落ちた。髪を掴んで引っ張ると、ごっそりと手の中に抜けた。
浜山は慌てて立ち上がり、洗面所に入ると鏡に映った自分を見た。
つむじの右下あたりが綺麗に禿げ上がっていた。
掴んだ髪をゴミ箱に放り込み、もう一度頭に手をやる。その脂気の感じられない髪をつまむ。引っ張る。ほとんど抵抗もなく、毛は抜けた。
抗がん剤の副作用だ。
髪を手ぐしですいてみる。何本も何本も、指に絡まって毛が抜ける。面白いくらいだった。足元に、床屋に行った時のように髪の束が落ちる。
覚悟はしていたものの、実際に目の当たりにすると衝撃だった。
俺が禿げる時が来るなんてな。
情けないやら、呆れるやらで浜山は俯いて目をしばたたかせた。ぱらり、と洗面台に短い毛が落ちた。拾ってみると、睫毛であった。
八月二十二日
「午後、見舞いに来る? そうか」
浜山は休憩室の端っこ、通話スペースで携帯電話に向かって話す。
「じゃあさ、帽子買って来てくれよ。うん。あとさ……なんていうんだ、お前が使ってるやつ。いや、ほら。化粧の……眉を描くやつ。うん。あれ、貸して欲しいんだ。いや、ちょっとはマシになるかと思ってな」
電話を切り、浜山はふうと息を吐いた。
一度抜け始めると早かった。
あれほどふさふさだった髪は根元からちょん切られたように抜け落ちた。僅かに残っていた部分も、むしろみっともないので自分で引っこ抜いた。それだけではない。睫毛や、眉毛まで薄くなり始めた。どちらかと言えばいかつい顔で通っていた浜山も、こうなってはまるで宇宙人のようだ。
鏡を見るのが怖くなり、洗面台に立つ頻度は減った。
代わりに、トイレの回数が増えた。
吐き気が止まらないのだ。吐いても吐いても、まだ吐き足りない。胃がむかむかし、腹筋が痛いほどである。すでに腹の中は空っぽで、トイレに行っても胃液しか出てこない。にもかかわらず、ベッドに戻ってほんの数分でまた吐き気が湧き上がる。
主治医に訴えると制吐剤を処方してくれるのだが、どうも浜山の場合効き目が悪いようだ。
一日中吐き続け、便器と見つめ合う日々。
満足に食事もとれないため、頬のあたりが目に見えて痩せてきた。こんな状況だが、水はたくさん飲むようにと言われている。尿をたくさん出さないと、良くないらしい。必死にコップを口に運ぶのだが、そのプラスチックの歯触りや、水の感触ですら吐き気を呼び起こす。飲んでは吐き、飲んでは吐く。
嘔吐するたびに涙が流れ、喉が痛んだ。
追い打ちするかのように、口中の粘膜にも副作用が現れ始めた。口内炎が五個も十個もでき、潰れてはまたその上にできる。喉はひりひりして、常に荒れている。口を動かすのも億劫になる。
しかし、感染症を防ぐため、まめにうがいをしなくてはならないのだ。
大の男が口内炎くらいで悲鳴をあげるなと言われるかもしれない。しかし、瞬間ならまだしも一日中、痛みに耐えるのは辛いものがあった。
ちくちく、じわじわ。
痛みと、吐き気。そして下痢に、脱毛。
食事は楽しめず、常に体がだるい。自分の体が壊れていくのを感じるのは、想像以上に精神を疲弊させる。
浜山はため息をついて、ソファに腰かけた。
俺は何のために生きているのだろう。
そんなことを思う。
死にたいわけじゃない。ただ、疲れた。この疲れを取るために、少しだけこの肉体を離れて自由になりたい、そう感じる。病気を治すためには、こんなに疲れなくてはならないのか……。
浜山は自分の頬を手のひらで叩いた。
弱気になるな。
医者は言っていた。少しの辛抱だ。抗がん剤治療が終われば、髪は再び生えてくるし、口内炎だって治る。心配する必要はない。癌をやっつける過程の、一時的な症状に過ぎないんだ。
もう一度頬を叩く。骨ばった頬を、弱々しく叩く。
そして立ち上がり、点滴棒を支えにしながら、ゆっくりと自室へと向かった。
八月二十三日
掌にシャワーの水流が降り注ぐ。当たっては砕け、細かい水の粒子として落ち、排水溝へと流れ去っていく。福原雅和はその逞しい体を壁にもたせかけ、天を仰いで湯を浴びていた。
血と脂と消毒薬と、そして石鹸の匂いがする。手には微かに緊張が残っていて、それを温水が優しく取り除いていく。
難しい手術だった。目を閉じる。冠状動脈の左前下行枝にバイパスを繋いだ瞬間の映像が鮮やかに蘇る。心臓は動いたままであり、血管は虫のように脈動している。そこにバイパス……患者の手首から持ってきた血管……を繋ぎ、新たな血液の道を作るのだ。繊細かつ迅速な手さばきが必要となる。
一歩間違えれば大出血。
死はすぐそこで舌なめずりをしている。
福原は患者の心臓の動きを読む。それを体内に取り入れる。自分と患者とが一体となる感覚。
ドッ、ドッ、ドッ、ドッ……。
患者と福原。二人の心臓が、ハーモニーを奏で始める。
相手のリズムに逆らってはならない。伴奏に主旋律を乗せるように、あくまで自然に滑らかに。鋏に似た金属製の道具……持針器を、本能で駆る。ほんの僅かの異常も見逃さぬよう、まばたきもせずに患部を見つめながら。脳は冷たく心は熱く。脇に立つ助手の息遣いが消え、福原に聞こえるのは互いの拍動だけ。流れるように針を繰った。無影灯の光を浴びて、持針器の持ち手が黄金色に煌めいた。
心臓が止まって見えたな。
福原は髪を洗いながら、つい数分前の手術の出来に満足して笑った。
救った。俺は、救ったんだ。俺がいなければ死んでいた患者を、生き残らせた。
シャワーを止める。片手でタオルを取り、かすかにカールがかかった真っ黒な髪に押し付けて豪快に拭く。
命を死神から取り返した手ごたえを確かめるように、福原は拳を握りしめた。
【NOT FOR SALE】
試し読みの無断複製、転売、配布等は禁止します
©Atsuto Ninomiya / TO Books.
「最後の医者」シリーズのお買い求めはこちらから!

- 最後の医者は桜を見上げて君を想う
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(上)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:638円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(下)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:594円(税込)

- 最後の医者は海を望んで君と生きる
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)