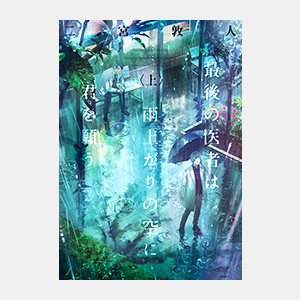- トップページ
- 最後の医者は桜を見上げて君を想う(5/5)
試し読み
最後の医者は桜を見上げて君を想う(5/5)
著:二宮敦人
音山晴夫は男子更衣室の前で待っていた。と、カーテンが開き、白衣をまとった福原雅和が出てきた。風呂上りらしく血色がいい。日に焼けた肌に、かすかに汗が光っている。音山は手を上げて声をかけた。
「やあ福原、お疲れ様」
「おう音山」
福原は同期生の姿を認めると白い歯を見せて笑った。手術前の獣じみた闘志が消え去り、福原は人懐っこい笑顔の美男子に戻っていた。
「小切開冠動脈バイパス手術だったんだろ。大成功だそうじゃないか」
「まあな。俺にかかりゃ、ちょちょいのちょいよ」
「あんな人間の中でボトルシップ作るような真似、よくやるよ……脳腫瘍の少年も成功だってな。脳外科も心臓外科もこなすなんて、信じられないよ。いっそ内科もやってくれないか、たまには長期休暇でも取りたいんだ」
「おいおいちゃんと働かないと、副院長権限で減給すっぞ」
福原は冗談っぽく音山の首に腕を絡めた。「それは勘弁」。音山もにやつく。医局ではこんなやり取りはできないが、二人になればいつでも友人同士に戻れる。音山はできるだけ自然にと意識して切り出した。
「ところで福原、昼飯まだだろ? 腹減ったんじゃないか」
「ああ、そういやそうだな……」
福原は腹に手を当てる。空っぽの胃が音を立てた。
「一緒に食堂行かないか?」
「いいね。俺、肉食いたい。今日はビーフステーキ二人前で決まりだ」
「手術後によく肉なんて食えるなあ……」
音山は呆れて笑う。福原は髪を掻き上げて言った。
「手術後だろうが前だろうが、肉食って力つけないとな」
一階のレストランは中央を衝立で仕切られており、一般患者が使えるスペースと病院関係者用のスペースとがはっきりと分かれている。
「ひょっとして手術が終わるまで待っててくれたのか?」
「まあ、そんなところ」
会話しながら福原と音山は中に入る。昼時を少し過ぎたため、レストラン内に人はまばらだった。並んだ白いテーブルの一つに座っている人影を見てとると、福原は顔をしかめた。
「おい音山。まさか……」
不機嫌そうに振り返った福原が、頭一つ分低い音山を見下ろしてきた。
「ほ、ほら。たまには同期三人で飯ってのもいいかと思ってさ。なかなか前みたいに集まることもできないし。顔を合わせて話すのって、大事じゃないか」
自分でも苦しい言い訳だと思いながらも、音山は半ば強引に福原の袖を引っ張る。その先にはテーブルに肘をつき、無表情でこちらを見ている桐子修司がいた。
「お前、謀ったな。最初から俺と桐子を会わせるのが目的だったろ」
じろりと、福原の視線が音山に向けられる。
「いいじゃないか、食事くらい。ほらビーフステーキだろ、食券買えよ」
「……」
福原はしばらく苦虫を噛み潰したような顔をしていたが、やがて観念したように食券機に五千円札を放り込み、ステーキ定食のボタンを連打した。
「こうして飯を食うのも久しぶりだなあ。そうだろ、桐子、福原」
音山はハンバーグを突き崩しながら笑う。横の福原、対面の桐子の顔を交互に見ながら話しかけ、時には不自然にむせたりしながら、必死に場を繋ぐ。音山の努力もむなしく、二人はただ目の前の食物を口に運び続けている。会話は一向に盛り上がらない。
がつがつと肉の塊、サラダ、スープと掻き込んでいく福原。健康そうな顎が上下する。たちまちのうちに一皿が空く。ぽつんと残ったクレソンもつまんで、口に放り込んだ。
一方で桐子はといえば、相変わらず妙な食べ方だ。天ぷらうどんに葱をたっぷり載せてすすっているのは別にいい。問題は衣と尻尾だけを食べられた海老の天ぷらである。残りの部分が美味しいはずなのだが。あげくの果て、半分ほどうどんを食べたところで満腹になったらしい。箸を置き、魔法瓶から白湯をコップに注いで飲み始めた。ふう、とため息などついている。
「桐子のその食い方、学生時代を思い出すよ」
音山が言うと、福原がふんと鼻で笑う。
「あの頃はかけうどんだったけどな。天ぷらはなかった」
「だよね。それにしても福原ときたらあっという間に外科部長で、副院長だもんなあ。おかげで絡みにくくなって困るよ」
「俺の実力じゃないよ。親の七光りってやつさ」
「いや、実力がなかったらさすがにそこまで行けないだろう。桐子も戸惑ってるんじゃないかい?」
音山は桐子に水を向ける。だが桐子はたった一言呟いただけだった。
「いや、別に」
「そ、そうか……ふ、福原は? ほら、桐子とあんまり話さなくなって、色々と……その、誤解があったりはしないかい」
「本当に強引な話の持っていき方をするよな、音山は」
福原は紙ナプキンで口の周りを拭く。それからもう一枚ナプキンを取ると、テーブルの上を簡単に拭いた。
「お前の魂胆はわかってんだよ。俺と桐子を仲裁しようってんだろ」
「それは……まあ……」
「言っておく。そんな気遣いは必要ない。いや、余計なお世話だ」
「だけど。君たち二人が仲たがいしているなんて、勿体ないと思うんだよ。前みたいに力を合わせれば、もっと……」
「無理な話だ」
福原は立ち上がる。椅子が床にこすれて大きな音が響いた。
「こいつとは、根本的な部分で相容れないからな」
そう言って桐子を指さした。桐子は白湯の入ったコップを持ったまま、物静かに向けられた指先を見つめている。
「お前の医者としての振る舞いの全てが気に入らない。いや、許せない。いいか、俺はお前を許さないぞ。そうだな、せっかくだからここではっきり言っておくか」
「おい、福原……」
音山の声など耳に入らないかのように、福原は桐子だけを見据えて続けた。
「お前は病院にいてはいけない。俺は、病院のために、いや患者のために、お前を必ず追い出してやる」
福原の背後で太陽が雲から顔を出した。影が逆光の中で浮かび上がり、桐子へと降り注ぐ。桐子が白湯を一口含み、答える。
「福原。君に、医者として何が正しいかを決める権利などないよ」
桐子は眩しそうに、目を細めて続けた。
「それを決めていいのは患者だけじゃないか?」
「……患者を殺す医者が、正しかったためしはないんだよ!」
福原は吐き捨てると、皿が載ったお盆を持ち上げた。
「じゃあな、音山。今後余計なことはするなよ」
そう言って音山の肩をぽんと叩くと白衣を翻し、大股で食器返却所へと歩き去っていく。その後ろ姿を見つめながら、音山はため息をついた。
桐子は何も言わない。ただ口を真一文字に結び、白湯の中で揺れる自分の影を眺めている。
ふと、PHSが鳴った。音山は一瞬自分のものかと思って胸を探る。その前で桐子がポケットからPHSを取り出して耳に当てた。
「はい桐子」
「先生。どこでサボってるんですか。患者さんと面談の時間です」
漏れ聞こえる声は、看護師の神宮寺千香のものだろう。
「予定に入っていたかな」
「入っていません。患者さんからのご要望で、勝手に入れました」
「そう。今行く」
桐子は短く言ってPHSを切る。それから魔法瓶の蓋を締めつつ、音山に言った。
「悪い。用事ができた」
「ああ、いや……うん。気にしないでくれ」
音山は曖昧に頷く。
「じゃあ、また」
桐子はそう言って軽く頭を下げると、お盆を持って立ち上がった。裸に剥かれた海老が、所在無げに丼の端で揺れていた。
八月二十五日
「例の案件、受注できましたよ」
「……そうか。良かった」
嬉しそうな堂島の声に、浜山は弱々しく答える。
「あれ、やっぱり悔しいですか? そりゃそうですよね、この喜びを分かち合えないのはそうですよね。でも浜さんのおかげだってみんな言ってますよ、元気出してくださいよ。浜さんらしくないなあ」
堂島に悪気はないのだろうが、点滴に繋がれたままでは、何を聞いても嫌味に聞こえてしまう。浜山は心の中の暗い思いをできるだけ隠そうと、端的に言った。
「ああ。わざわざ連絡をありがとう」
「いえ。それより浜さん、なかなかお見舞いに行けずにすみません。案件決まって、急に忙しくなりまして。俺も飛び回ってんですよ。落ち着いたら、必ず」
「そんなのいいよ。無理すんなって」
「いえ。行きますから」
「来なくていいよ。大丈夫だ。仕事に集中してくれ」
人に会える顔ではないのだ。顔色は悪く、毛は抜け落ちている。何よりも気力が湧かない。この電話だけでも疲れてしまうくらいなのだ。気を張っていないと、すぐに吐きそうになる。
「じゃあ、また」
まだ何か言いたそうな堂島をよそに、ほとんど強引に電話を切る。
それから携帯の画面をぼんやりと見つめた。
気になるのは、案件のことではなかった。浜山が長期の休暇を取るにあたり、会社がどう判断するかが気がかりだ。有給があるうちはまだいいが、それが切れたら? 休職扱いにしてくれるだろうか。うちは小さな会社だ。社長は悪い人ではないが同時にシビアでもあり、最悪首を切られるかもしれない。病気なのだから、そこまではされないと信じたいが……。
浜山は憂鬱な気分で病室へと戻った。
昼ご飯をほとんど口にも運べぬまま残し、ベッドでぼんやりと天井を見つめていると、扉が開く音がした。
痩せた老人が入ってくるのが見える。浜山と同じく急性骨髄性白血病の老人だ。
その姿を目で追う。点滴棒を持っていない。手ぶらであった。
のそのそと隣のベッドに入った老人に、浜山は声をかけた。
「抗がん剤治療、終わったんですか? おめでとうございます」
老人は口をへの字にしたまま、じろりと浜山を見た。そして首を横に振った。
「終わったわけじゃない。やめたんだよ」
「やめた……?」
「死神に相談して良かった。わしはもう降りると決めた」
老人は吐き捨てるように言うと、どっかとベッドに腰を下ろした。そして深いため息をつき、脇の机に置いた写真立てを見た。そこにはふっくらとした男性が、海岸で女性と一緒に笑みを浮かべる写真が入っている。
降りる、とはどういうことだ? 浜山は老人の背を見る。体は痩せこけ、骨が浮き出ている。頭の毛はほとんど抜け落ち、産毛のような白い毛が数本、飛び出ているばかり。その姿は写真とは別人のようだったが、浜山とは似ていた。
「この病院は地獄だ。どこにも出口のない地獄。あんたもそうは思わないか」
「どういうことですか」
「まだそこまで追い詰められてはいないか。まあ、いい。一つアドバイスだ。どうしようもなくなったら、皮膚科の桐子という医者に面談を申し込んでみろ。神宮寺という看護師に言えば取り次いでくれる」
「ちょっと待ってください、皮膚科ですって? 皮膚科の医者が、何をしてくれるんですか」
「何でも相談できる。どんな病気についても、だ。患者の中では有名な医者だよ。わしも噂に聞いて、面談を申し込んだんだ。七十字の死神、などと物騒な仇名が付いてはいるが……」
老人はふと遠くを見るような目をした。
「わしは、名医だと思うね」
浜山が何か聞こうとする前に、老人はしゃっとカーテンを引いてしまった。視界が遮られ、世界が隔たれた。
老人はその日のうちに、病室を去っていった。
あとには空っぽのベッドだけが残された。
【NOT FOR SALE】
試し読みの無断複製、転売、配布等は禁止します
©Atsuto Ninomiya / TO Books.
「最後の医者」シリーズのお買い求めはこちらから!

- 最後の医者は桜を見上げて君を想う
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(上)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:638円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(下)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:594円(税込)

- 最後の医者は海を望んで君と生きる
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)