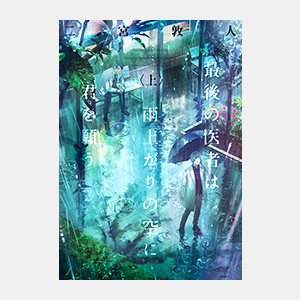- トップページ
- 最後の医者は海を望んで君と生きる(1/5)
試し読み
最後の医者は海を望んで君と生きる(1/5)
著:二宮敦人
プロローグ
二十六歳、結婚三年目のクリスマスイブ。こんな電話をするなんて、考えたこともなかった。
いつの間にか、僕は白い天井を眺めていた。
ここはどこだろう。
あたりは騒がしい。断続的に電子音が鳴っている。早足で誰かが歩いている。よく聞き取れないけれど、緊迫した様子の声がする。銀色の棚に薬品のボトル。どうやら病院のようだけど、なぜここにいるのか思い出せない。
僕はストレッチャー……いわゆる車輪つきの担架に乗せられていた。背もたれは軽く上げられ、ゆるく座るような体勢だ。スーツを身につけたままで、靴は履いていない。
人を呼び止めようとした瞬間、胸の奥に激痛が走り、動けなくなってしまった。巨人の掌で、心臓を握りつぶされているようだ。全身に冷や汗が滲んでくる。
「先生、こちらです」
看護師が一人、白衣の男性を連れてやってきた。
「辻村浩平さん、初めまして。私は医師の室井と申します」
その医者はすぐ横から僕の目を覗き込み、微笑んでみせた。返事をしようとしたが声が出ない。仕方なく頷き返す。
「ここは武蔵野七十字病院の救命救急センターです。あなたはお店で気分が悪くなり、動けなくなっていたところを、救急車で当院に搬送されました。これから重要な話をします。よく聞いてください。わからないことがあれば何でも仰ってください、いいですね」
はきはきとした聞き取りやすい声だが、やや早口だった。
「はい」
今度は返事ができた。
「さきほど超音波を使って、あなたの心臓を診ました。動きが悪くなっていて、このままだと止まってしまうおそれがあります。劇症型心筋炎が疑われます。ばい菌やウイルスが心臓に入り込んで、悪さをする病気ですね」
「はい」
現実味が感じられないまま答える。
「これからあなたの体に管を入れて、心臓の代わりをする装置を繋げます。心臓には少し休んでもらい、その間に回復を待つということです。きっと良くなりますから、一緒に頑張りましょう」
「はい」
「辻村さん、スマートフォンか携帯電話はお持ちですか?」
「あ、はい。スマホを……」
医者は傍らの看護師を振り返った。
「辻村さんの私物は」
「こちらに。失礼します、探させていただきますね」
看護師は軽く会釈すると、ストレッチャーのすぐ横の布袋を開き、手を突っ込んだ。見慣れたものがいくつも見えた。
コート、手袋、マフラー。黒のビジネスバッグに、濡れた折りたたみ傘。
そうだ、雪が降っていたんだ。
記憶が一気に蘇る。
今朝はよく晴れていて、暖かかった。僕はコートだけで平気だと言い張ったけど、君は差しだした折りたたみ傘を引っ込めずに言った。
──夜には気温が下がるし、降水確率も三十パーセントだよ。このところ風邪気味なんでしょう。悪いことは言わないから、持っていきなよ。手袋とマフラーも忘れずにね。
もう長い付き合いだから、こういうことでは逆らわないって決めている。言われた通りに鞄に入れて、二人一緒に家を出た。駅までお喋りしながら歩いて、改札前で手を振って別れた。僕はJR、君は地下鉄。薬指で結婚指輪がきらりと光った。
──早く帰ってきてね。
もちろん。料理の材料はばっちり買い込んである。予約したケーキは、君が受け取ってきてくれる。あとは君へのクリスマスプレゼントを買うだけだった。
定時に仕事を終わらせて、上司に帰りますと宣言した。パソコンをシャットダウンしてふと窓を見たら、ちらほらと白い粒が舞っていた。さすがだね。傘を握りしめて、思わず笑っちゃった──。
「スマホはどこに入れていますか」
声をかけられて我に返った。看護師がバッグの中をがさごそ漁っている。
「コートのポケットか、鞄のサイドポケットだと思います」
「あ、ありました」
見慣れたスマートフォンを持ち、看護師がこちらにやってきた。差し出されるままに受け取る。僕がきょとんとしていると、医者がゆっくり、しかしはっきりと言った。
「連絡をしておきたい方がいたら、今、してください。何か伝えたいことがあれば、伝えてください」
「え?」
医者が掛け時計を確かめる。
「時間は十分、いや五分でお願いします。その間に電話をしてください」
困惑していると、医者が真剣な表情で続けた。
「私たちは全力を尽くします。ただ非常に危険な状況です。はっきり言いますね。これがあなたが誰かと話せる、最後の機会になる可能性があります」
何を言っているのかわからない。いや、わかりたくない。
手が震え始めた。視界の端がぼやけていく。
「辻村さん。頑張ってください、さあ」
横から看護師が僕の背に手を当ててくれた。促されるまま、僕は画面のロックを解除し、電話のアイコンに触れる。履歴のほとんどを埋めている、君の電話番号をタッチして耳に当てた。
鳴り始めた呼び出し音を聞きながら、あたりを呆然と眺める。
これが最後。そんなばかな。
急に言われたって困るよ。一体何を言えばいいんだ。たった五分だなんて。その五分が、今も数秒ずつ過ぎていく。
冷や汗が垂れる。胸の奥が苦しい。
お願いだ。冗談だと、夢だと、誰か言ってくれ。どうして? どうしてこんなことになった?
会社を出て、傘を差して、僕は百貨店に寄った。マフラーやバッグもいいと思ったけれど、スペイン製のキャンドルスタンドに目が留まった。色つきガラスでできていて、ろうそくをつけると部屋が海の中のように照らし出される。可愛いね、と笑う君が目に浮かんだ。僕はこれいくらですか、と聞こうとして、そこで胸が苦しくなって──。
呼び出し音はまだ続いている。
早く出て欲しい。いや、今出られても何も言えない。だけど何か言わなくちゃ。何を言えばいい。この気持ちを、どんな言葉にすればいいのか。
呼吸が浅い。さっきから何度も瞬きしているのに、目が乾く。
二十六歳、結婚三年目のクリスマスイブ。
ついさっきまで、百貨店で買い物をしていたんだ。クリスマスソングを聞きながら、君の笑顔を想っていたんだ。
こんな電話をするなんて、考えたこともなかった。
第一章 とある伴侶の死
武蔵野七十字病院の若き院長、福原雅和は大きな体をソファに横たえ、仮眠をとっていた。広い院長室は散らかり放題。パソコンデスクや応接用の大きなテーブルはもちろん、あちこちの床にまで本や論文のコピーが山積みで、その隙間にマグカップやペンなどの小物が潜んでいる。
片付けはどうしても後回しになってしまうのだ。
今日も朝から回診したのち三時間に及ぶ手術を二つこなし、会議に出て、遅い昼飯をかき込み、やっと一休みしたところだった。
浅い眠りの中で、夢を見ていた。
あたりは暖かい太陽の光でいっぱい。楽しげな音楽の中、笑顔の人々が行き交う。ステンレスのテーブルにはバスケットに入ったお弁当が置かれていて、その向こうには懐かしい面影が見えた。
「母さん!」
福原は思わず叫んだ。母親は大きな麦わら帽子をかぶり、にこにこ笑っているようだった。忘れもしない、少年だった頃、たった一度だけ連れて行ってもらった遊園地。思い出のあの日に、福原はいた。
「俺、元気でやってるよ。何から話したらいいかな」
伝えたいことはたくさんあった。
クラス委員長になった。作文で賞状を貰った。高校では特進クラスに選ばれた。体力をつけるためにジョギングも始めた。
「医者になると決めてからは、一日中勉強してたよ。東教医大に受かった時には嬉しかった。父さんはどうせなら東大を目指せと言っていたけどね」
優しい微笑みを浮かべる母親の前で、福原はまくしたてる。
「でも医学部って、入学してからの方が忙しいんだ。基礎医学は頭がおかしくなるくらい暗記漬けだし、解剖実習や臨床実習の大変さときたら。国家試験だって控えてる。無事に医者になってからも勉強は続けるし、手術の練習だってしなくちゃならない。ティッシュぺーパーを心臓に見立てて、爪の先みたいな針でこう、縫い合わせるんだよ。何枚も何枚も」
福原が手つきを真似してみせると、微かに相手が頷いた気がした。そこでふと冷静になり、福原は視線を落とした。
「でもね、どうってことないよ。母さんに比べれば」
俯いたまま続ける。
「俺、改めて思うんだ。母さんがどれだけ強かったか。癌の末期なのに、弱音一つ吐かなかったね。決して諦めず、闘い続けていたよね。最後の力を振り絞って、俺を遊園地に連れて来てくれた。お弁当を朝から作って、俺の好きなおかずばかり、こんなに」
再び顔を上げた時には、涙で視界がぼやけていた。
「お棺の中でまで、笑ってたよね」
目映い光の中、母を感じる。
「俺、母さんにさようならを言った後、強くなるって決めたんだ。誰かのために、一緒に闘える人になりたかった。だから俺は平気だったよ、勉強だって何だって。そりゃ躓いたこともあったけど、母さんを思えば頑張れた」
どこか遠くで電話が鳴っている。
「がむしゃらにやっていたら、俺……自分でも驚きだけど、院長になれたんだ。でも、まだ満足はできていない。もっと強くなって、たくさんの人を助けたい。苦しんでいる人はみんな助けてやりたい。この世から悲しい思いをする人が、いなくなったらいい。だから俺……」
少しずつ電子音が大きくなる。
「あ、待って、母さん。もう少しだけ」
淡く滲んだ視界の中で母の姿が遠ざかっていく。思わず手を伸ばそうとしたが、体が動かない。不快な音だけが、耳元で響き渡る──。
そこで夢から覚め、がばと福原は起き上がった。かけていた薄手の毛布が床に落ちた。
「はい福原」
額の汗を拭き、素早く電話に出る。
「院長先生。休憩中のところ申し訳ありません」
「どうした」
「救急の応援、お願いできますか。さっき心筋炎の方が来たところなんですが、近くで交通事故が起きたそうで。これから高エネルギー外傷が二人、来ると」
「よし、すぐ行く」
福原は受話器を置くと、汚れた白衣を脱いで放り投げ、きびきびと大股で歩き出した。頭は冴え、熱い闘志が腹の底から湧きあがってくる。
せっかくの仮眠を妨害された、などとは考えもしない。福原にとっては、患者を受け入れない方がずっと嫌なのだ。
さあ、助けるぞ。
見ていた夢のことなど、すっかり意識から消え去っていた。
【NOT FOR SALE】
試し読みの無断複製、転売、配布等は禁止します
©Atsuto Ninomiya / TO Books.
※この試し読みの内容は書籍収録内容と一部異なる場合がございます。
「最後の医者」シリーズのお買い求めはこちらから!

- 最後の医者は桜を見上げて君を想う
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(上)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:638円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(下)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:594円(税込)

- 最後の医者は海を望んで君と生きる
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)