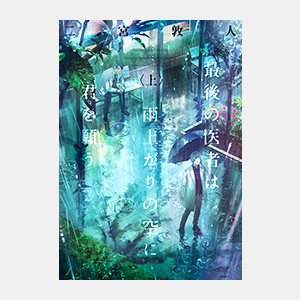- トップページ
- 最後の医者は海を望んで君と生きる(5/5)
試し読み
最後の医者は海を望んで君と生きる(5/5)
著:二宮敦人
「この間も手術しましたよね。浩平の頭を切ってまで」
「はい」
福原の声には、悔しさが微かに滲んでいる。
「あの手術が失敗だったということですか」
「いえ、成功でした。血腫も脳動静脈奇形も、完全に取り除きました。ただ、今回の出血はまた別の場所なんです」
「どうしてそんなにあちこち血が出るんですか」
「それなんですが……」
福原は早口ではあったが、丁寧に説明してくれた。
そもそもエクモやインペラという機械で血を送る行為そのものが、出血のリスクとなること。最初の出血については、浩平の体質、それから血が固まりにくくなる薬、抗凝固薬を少量ながら投与していた影響があったこと。しかしこの薬を使わないと、今度は血管の中に血の塊、血栓ができやすくなる。血栓は体のあちこちで詰まる危険があるほか、エクモの回路にも入り込む。詰まった回路の交換はできるだけ素早く行うとはいえ、その最中は心臓が止まっているのと同じ状態になるため、体にダメージが出てしまう……。
藍香は正直、話についていくだけで精一杯だった。
それでもぎりぎりの状況の中、医者が懸命に最善を尽くし、浩平の命を繋ぎ止めようとしているのは伝わってきた。
スマートフォンを握る手に、ひどく力が入っていた。
思い通りにならない病状が悔しい。せめて怒りをぶつける相手が欲しい。しかし医者を憎むのは筋違いだった。
福原が繰り返した。
「手術のご同意を」
「わかりました。どうかよろしくお願いします」
「ご来院された際に、手術の同意書にご記入ください」
頷き、藍香は聞いた。
「あの。助かるんですよね」
「助けますとも。全力で」
迷いのない声だった。彼を信じ切れたらどんなに楽だろう。だが、この医者はいつかもそう言った。
藍香はクッションを抱きしめ、しばらく顔をうずめた。腹の底でうごめき始めた不安に必死に蓋をして、立ち上がる。淡々とコートに袖を通し、ハンドバッグを手に取る。軽くリップグロスだけ唇に引いて、部屋の電気を消し、病院に向かって家を出た。
†
食堂のメニューに七草がゆと書かれているのを見て、福原は久しぶりに日付を意識した。
ついこの間、元旦だったような気がするが。
ふと気づくとあっという間に時間が過ぎている。それだけ一日一日が濃く充実している。しかし不思議と疲れや迷いは感じない。朝起きれば元気いっぱい。三時間しか寝ていなくても平気で仕事ができ、急患があればいつでも飛び出していく。
福原は自分の体力、気力に自信を持っていた。たとえるなら、ろくに休まずとも、どこまでも走り続けられる名馬。自分はそういう力を生まれつき与えられたらしい。が、たまに患者が少ない日など、なぜか不安が頭をよぎったりもする。自分は一度足を止めたら、二度と立ち上がれないのではないか──。
ステーキ定食を注文しようとした時、PHSの電子音が鳴った。
「はい、福原」
福原は列を離れて電話に応じる。
「そうか。わかった」
眉間に皺を寄せて頷く。
「よし、スタッフを集めてくれ。大丈夫だ、すぐ行く」
列に戻れるよう、一人の職員が場所を空けていてくれたが、福原は笑って首を横に振ると、空のトレイを返却口に下げた。
もう、腹一杯食べるような気分ではなくなっていた。
会議室に入ると、すでに他のスタッフは全員揃っていた。みな、暗い顔をしている。
「辻村さん、また脳出血だって?」
福原はため息交じりに席につく。
「はい。これで三回目になります」
電子カルテに目を落とす。
辻村浩平さんは入院からすでに二週間が経過。しかし未だに心臓が動き出さない。その上、出血が依然としてコントロールできない。さらに、数日前からは腎機能が低下し、透析が必要になっていた。
「この状況では、もう……」
誰かの呟きを最後に、会議室は静まり返った。
みな、うすうす結論はわかっていた。だがちらちらと福原を見るばかりで、口にはしない。
福原が奥歯を噛みしめる音が響いた。
「何か方法はないのか」
頭を抱え、ほとんど独り言のように漏らした。福原がそう言うということは、もはや病院としての敗北宣言に等しかった。
「ここが治療限界です」
スタッフの一人が言う。
「もはや打つ手がありません。不可逆的な脳へのダメージがあるため、補助人工心臓も適応外になります」
「わかってる」
福原は拳を握りしめる。力一杯握りしめたその手に、筋肉が浮き上がっていた。また別の医者が言う。
「本当なら、最初の出血時に終わっていました。あれから一週間以上もったんです。私たちは最善を尽くしたと思います」
「そんな言葉。何の慰めにもならない」
深い怒りを押し殺したような福原の声。相手は一瞬ひるんだが、やがて悲しげに続けた。
「もはや回復は望めません。緩和ケアに切り替えるタイミングかと」
福原は顔を上げ、充血した瞳で相手を睨みつける。だがすぐに頭を振ると、苦虫を噛みつぶしたような顔で俯いた。
「そうだな。すまない」
スタッフに八つ当たりしたって仕方がないのだ。
大きくため息をつく。息がどこまでも吐けそうな気がした。体中の空気が、全部出て行くようだった。椅子の固さが、部屋の冷気が、しんしんと伝わってくる。
「助けたかった」
ぽつりと零れた言葉は、静寂の中にかき消えていく。
「これまでのみんなの努力に感謝する」
福原は顔を上げ、仕切り直した。
「辻村さんのご家族は?」
「今、奥さんがちょうどいらしてます」
看護師の言葉に頷く。
「わかった。これから行こう」
それが何を意味するのか、全員が理解していた。
福原はスタッフを一人引き連れてICUに入り、ゆっくりと歩いていく。
辻村浩平は一番奥のベッドに寝かされていた。すぐ横で、妻の辻村藍香が寄り添うように座り、愛おしそうに夫の顔を覗き込んでいる。今なお、装置は精力的に血を入れ替え続けているが──浩平の心臓はほとんど動いていない。
「どう、具合は」
藍香の声が聞こえてくる。
「私は元気だよ。毎日のストレッチも続けてる。こうくんもちょっとだけ、顔色良くなったかな」
その手が優しく撫でている顔を、福原は見た。
入院生活と度重なる手術により、浩平の姿は変貌している。
それは一言で言えば悲惨だった。
瞼は赤く腫れ上がり、うつろな瞳の焦点は合っていない。頭は左右が非対称、左側がむくんで膨らんでいる。黒くて艶のあった短髪はすっかり剃られ、頭皮にはみみず腫れに似た手術の跡が走り、医療用ホチキスで留められている。口には太い管、鼻からは細い管、そして頭からはケーブルが出て横の装置に繋がり、首にも管が入っている。見た目ではわからないが、左の頭蓋骨の一部は外されていて、腹の皮膚の下に埋められている。布団をめくれば、手首や足の付け根から管が出ているのも見えるだろう。
「かぶれちゃって、可哀想に」
チューブの触れる唇の横は、赤く爛れてしまっている。
「そうそう、おせち料理、凄かったよ」
広い病室に、藍香の声と電子音が響く。
「受け取った時、重くてびっくりしたもん。一段目を開けたらロブスター? でっかい赤い海老が、ドーンと。初めて食べたよ、噛み応えがあった。それから甘露煮にも驚いたな。緑色の梅の実みたいなのがコロコロ入ってるから何かと思ったら」
口に放り込んでかじる仕草をしてみせる。
「若桃だって。育つ前に摘み取った小さな桃。あんなに爽やかで甘いなんて知らなかったな。舌触りが滑らかで、種まですっと歯が入るんだよ。こうくんは食べたことあったの? それとも食べてみたくて注文したのかな。どこから見つけてくるのか、いつも不思議に思うよ」
浩平は答えない。
「安心してね、ロブスターも甘露煮も、まだたくさん残ってるからね」
藍香が俯く。声が震えていた。
「そもそも私一人には多すぎるよ。早く食べないと、傷んじゃうよ」
膝の上でぎゅっと握り込まれた拳。
「早く帰ってきてよ。食べてよ。あんなにたくさん頼んでさ、私、あんなに、どうしたらいいか……」
福原は一歩進んだ。
「辻村さん」
ようやく藍香はこちらの存在に気づいたようだった。怯えたような瞳が福原に向けられている。
「別室でお話しできますか」
どうしても低い声になってしまう。
「はい」
顔をこわばらせて藍香が頷いた。
【NOT FOR SALE】
試し読みの無断複製、転売、配布等は禁止します
©Atsuto Ninomiya / TO Books.
※この試し読みの内容は書籍収録内容と一部異なる場合がございます。
「最後の医者」シリーズのお買い求めはこちらから!

- 最後の医者は桜を見上げて君を想う
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(上)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:638円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(下)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:594円(税込)

- 最後の医者は海を望んで君と生きる
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)