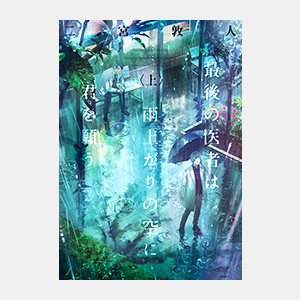- トップページ
- 最後の医者は海を望んで君と生きる(4/5)
試し読み
最後の医者は海を望んで君と生きる(4/5)
著:二宮敦人
福原は看護師の一人に指示を出すと、一礼してその場を離れる。看護師がそっと歩み寄り、藍香の背に手を当てた。気丈にも藍香は頷き、歩き出した。だが数歩足を動かしたところで止まり、ゆっくりと頭に手を持っていき、抱えた。そのまましばらく俯き、床を眺めてから。
毛髪ごと、頭皮を掻きむしった。
†
福原はCT室で、診療放射線技師と一緒にモニターを睨みつけていた。白くて大きなドーナツを思わせるCT装置と、その穴の部分に頭を突っ込むようにして寝かされている辻村浩平がガラス越しに見える。やがて、X線を通して画像化された脳の様子が、モニターに映し出される。その白黒で非対称な画像を見るなり、福原の顔色が変わった。
「合併症か。左脳半球から出血……しかも、脳ヘルニアを起こしている」
頭蓋骨というパッケージに、脳という豆腐が収まっているとする。今、パッケージの中で出血が起き、血の塊──血腫ができてしまった。その分、行き場をなくした豆腐が押し出されているのだ。瞳孔不同は、目の動きに関わる神経、動眼神経が押されたためであった。
「この年齢では珍しいですね」
診療放射線技師が呟いた。
「このままでは脳幹部が潰れてしまう」
脳幹は生命維持を司る中枢だ。つまりこの状況は、死神の鎌が首筋に触れ、皮を切り裂きつつあるのと等しかった。
「そのまま造影CTも追加で頼む。できた順でいい、すぐに送ってくれ」
福原は診療放射線技師に、より詳しく血管の様子を撮るように指示すると、CT室を飛び出した。
今すぐ手術して血腫を取り除かなければ、彼は死ぬ。
ICUに戻りつつ次々にスタッフに指示を出し、手分けして動く。手術室を手配し、家族から手術の同意書を取る。
「造影CT、送ります」
診療放射線技師からの電話連絡を受け、福原は会議室の一つに飛び込むと、ノートパソコンにかじりついた。送られてきたCTアンギオグラフィを睨みつける。
複雑に組み合わさった木の根のような画像。その輪郭をたどれば脳の形をしているのがわかる。造影剤を注射し、X線を照射して描出した、脳内の血管の様子だ。その一点を福原は見つめた。
血腫はここだな。周りの血管を押しのけている。
部屋に看護師が飛び込んできた。
「福原先生、手術室準備できました」
「ああ」
福原はディスプレイから目を離さず、返事をする。
血腫の周りに淡く細い血管が見える……微かな違和感。
肉食獣のように目を細める。
「福原先生!」
「今行く」
くそっ、時間がない。
福原は立ち上がり、ノートパソコンに背を向けた。
手術準備室には、スタッフたちが勢揃いしていた。マスクをつけ、帽子をかぶり、手指を消毒する。空気は張り詰め、みな不安そうな顔をしていた。
「大丈夫だ」
福原は明るく笑ってみせる。
「間に合う。全員で力を合わせればきっとできる。俺たちは、そのために腕を磨いてきた」
スタッフの顔に笑みと血色が戻ってくる。それぞれ目を合わせ、頷き合う。
「さあ、助けに行くぞ!」
福原の檄と共に、手術室の自動扉が開いた。
命を救う闘いが、再び始まった。
福原は辻村浩平の頭をメスで切開していく。皮膚と筋肉の奥から頭蓋骨が現れる。
「ハイスピードドリル」
電動のドリルを骨に押し当てる。穴を四か所開け、次に穴と穴とを繋ぐように切断し、取り除く。切手よりも二回りほど大きい、四角い窓が骨に開き、柔らかい膜が現れた。
「硬膜がパンパンに張っている。脳の圧が上がってるんだ」
慎重に刃を入れ、膜を切り開く。この奥はもう脳だ。その人をその人たらしめている臓器。脆く、壊れたら取り返しのつかない場所。
さあ、ここからだぞ。
福原は目を閉じ、ゆっくりと息を吐いた。そしてマスクの中、誰にも聞こえない声で、己に言い聞かせた。
──死ね。
もう一度、指をほぐしながら。
──失敗したら死ね。いいな、福原雅和。
覚悟が全身の隅々まで行き渡ったのを感じてから、目をかっと開く。
「始めよう」
清潔なビニールに包まれた手術顕微鏡を、骨窓の中がよく見える位置に固定する。
「モニタリング、目を離すなよ」
潜望鏡を覗き込む潜水艦長のように接眼レンズに食らいつき、フットスイッチを踏んだ。何十倍にも拡大された術野を、ハロゲンランプとLEDの光が鮮明に照らし出す。その中でマイクロ剪刀と鉗子を操り、病巣に向かって最小限の動きで進んでいく。
急げ。だが焦るな。
死んで白くなった脳細胞たちが見える。だが、まだ健康な脳細胞もある。余計な傷をつければ、どんな後遺症に繋がるかわからない。記憶障害、手足の麻痺、そして死。今、福原の指先は、生と死とが紙一重で繋がる、危うい神秘の領域に入り込んでいた。
額に汗が滲む。できるだけ瞬きもしない。
「血腫があったぞ」
赤黒くどろっとした血の池を見つけ、福原は呟いた。
「吸引管を」
細長いストローのような器具を受け取り、そっと差し込む。スイッチを入れ、溜まった血を吸い出していく。
その時だった。
突然、目の前が赤く染まった。
「先生、出血です」
助手が悲鳴のような声を上げる。福原の顔にまで飛沫が飛ぶ。
「わかってる」
吸引管で血を吸い出すが、まるで追いつかない。みるみるうちに術野が赤い液体で満ち、頭蓋骨の端から零れ出す。やがて目の前は赤一色、何も見えなくなってしまった。手術室に緊迫した空気が広がる。
「脈拍急上昇しました、百三十!」
看護師が声を上げる。さらに、その数値は徐々に下がっていく。
「九十。七十。六十、五十……」
命の灯が消えていく。福原は奥歯を噛みしめた。
落ち着け。出血する直前、何か異様なものが一瞬、見えた。あれは何だった? 思い出せ。考えろ。
脳裏をCTアンギオグラフィの画像がよぎる。血腫の周りにあった、淡く細い血管。微かな違和感──。
「二十、だめです。心臓、止まります!」
悲痛な声が飛ぶ。
終わった。
あたりに重い霧のような絶望が立ちこめる。この世から辻村浩平という人間は永遠に失われた。スタッフの一人が肩を落とし、項垂れた。
まだだ。
福原は諦めない。藍香の姿が瞬間、脳裏を走る。
彼には未来がある。帰りを待つ人がいるのだ。逝かせてたまるか。助けるんだ。俺はそのためにここに立っている。
「止血鉗子」
渡された銀色の器具を受け取り、構える。
そっと、静かに。止血鉗子の先端を赤い海に沈めていく。福原は無意識のうちに目を閉じていた。どうせ血で見えないのだから同じだ。見るな。感じるんだ。鉗子の先端が触れるものを、己の指で触れるように。
ここだ。
直感か、はたまた何か大きな意思に導かれたのか。福原は極小の点を狙い澄まし、鉗子の先端で押さえ込む。本能で動き、後から理解が追いついた。直後、一気に術野から血が引き始めた。
「脈拍、上がりました、戻りました! 五十、六十……安定してきました」
歓喜を隠せない様子で看護師が叫んだ。
「見ろ。ナイダスだ」
福原は小さく息を吐く。止血鉗子が押さえる先では、細い血管が蛇のようにぐちゃぐちゃに絡まり合っていた。
「脳動静脈奇形だよ。わかるか、先天性の異常血管だ。この若さで出血したのも、たぶんこいつのせいだ」
助手はただ、ぽかんと口を開けるばかりだった。
「十万人に一人という病気ですよ。それをあの状況の中、一発で見抜いて止血したんですか」
「ほら、ぼうっとしている場合じゃないぞ。クリップ鉗子をくれ」
福原はナイダスの処置に取りかかった。入り組んでいる異常な血管の入口と出口を、小さなチタニウム製クリップで止めてから、切除する。
「奇跡だ」
誰かが独り言のように呟いた。
「違うさ」
手を止めず目を離さず、福原は言う。
「最後まで諦めなかったからだ。きっとどこかに道はある。自分を信じろ」
みな、熱い眼差しを福原に向けている。
「さあ、あと少し。気を抜くな」
福原は自分にも言い聞かせるつもりで口にすると、作業を続けた。
長い闘いを終え、シャワーを浴びて院長室に戻ってくると、さすがに疲労感が全身を包んだ。福原はコーヒーメーカーにカップをセットしてボタンを押し、芳香に包まれながらソファに腰を下ろす。やがて出来上がったコーヒーを飲むのも忘れ、眠りに落ちていった。
夢の世界は薄い靄に包まれていたが、すぐに福原は気づいた。
あの遊園地だ。
煌びやかな装飾。音楽が聞こえてくる。石畳の上、陽光を受けて少年の福原は駆けて行く。あたりを見回して、すぐに目的のテーブルを見つけた。
「母さん。何だか最近、よく夢で会えるね」
椅子にぴょんと飛び乗って、母親を見上げる。
「さっき手術をしてきたんだ。危機一髪だったけど、うまくやれたよ。みんな驚いてた」
相手はにっこりと微笑んでくれた。
「考えてみれば俺、ずいぶん腕を上げたよね。ゴッドハンド、なんて週刊誌に特集されたこともある。目標にしてくれている若手もいる。昔と比べると信じられないでしょう、母さん?」
ひとしきり胸を張ってから、福原は視線を落とした。
「でもね、俺、まだまだなんだ」
冷たい風が吹き抜けていく。
「頑張っても頑張っても、この手をすり抜けていく命がある。助けられるのはほんの一部だけ。時々しんどくなるよ。ひよっこの頃の方が楽だったかもしれない。少し上達するだけでも、どんどん助けられる人が増えていくからね。だけど今は、分厚い壁に阻まれているような気がする」
母親が何かを気にしているように感じられた。福原はあたりを見回す。
「そういえば父さんはどこに行ったんだろうね」
靄の中に目を凝らしたが、人影がいくつか浮かんでいるだけだ。
「きっとトイレじゃないかな。心配いらないよ、あいつは殺したって死なないような男だから」
ふと、一人の男が姿を現した。優しそうな顔、少しお腹に肉のついた体形。
「あれ? 音山じゃないか。どうしてここに」
音山は黙ったまま、穏やかな表情でこちらを見ている。
「母さん、紹介するよ。音山晴夫。大学でできた友達なんだ。もう一人、桐子って奴もいるんだけど。そいつは少し、いやだいぶ変わってる。あれ」
音山は車椅子を押していた。そこに一人の痩せこけた老人が座り、福原を見上げている。眼光は鋭く、仏頂面だ。
「父さん……?」
父はしばらくこちらを睨んでいたが、やがて目を伏せた。ほんの一瞬、柔らかい表情を見せたような気がした。
「何だか変だな。音山、どうして父さんと一緒にいるの」
返答はない。みな、黙ったままだ。
福原はだんだん怖くなってきた。
「あっ」
三人が遠ざかっていく。
「待ってよ、みんな」
いや、違う。みなはそこを動かない。福原だけが現実に引き戻されていくのだ。そんな福原を三人はぼんやりと見つめている。何か言いたそうな、その目──。
眠りから覚めた時、福原は冷や汗をかいていた。
そよ風にカーテンが揺れ、窓から暖かな光が差し込んでいる。平和そのものの院長室を見回しても、しばらくこっちが現実だと飲み込めなかった。
やがて大きなため息をつき、ハンカチで額を拭いてから、すっかり冷めてしまったコーヒーをすすった。
内容は忘れたが、気味の悪い夢を見たという感覚だけが残っている。窓のそばに立ち、太陽の光で体を温める。まだ心臓がどきんどきんと脈打っていて、嫌な感じだった。
辻村浩平の脳内で再び血管が破れたのは、その一週間後。年明け早々の出来事であった。
†
藍香はソファに深く座って膝を抱えたまま、ぼうっと壁の模様を眺めていた。
カレンダーの一月三日という文字が、無意味な記号に感じられる。大晦日もお正月も、どこか遠い国で行われている祭りのようだった。
浩平が入院してからというもの、藍香の生活の中心は病院だった。毎日病院に出かけては面会申し込みの紙に記入し、札を貰ってICUに入る。意識のない浩平に話しかけ、十五分が過ぎた頃に出る。タイミングが合えば福原に病状の説明をしてもらう。すぐ帰る気にはなれず、かといって他に行く当てもなく、院内の喫茶店で飲み物を買い、中庭で病室を見上げながら時間をかけて飲む。その繰り返し。
同じように年末年始などない人が、病院にはたくさんいた。
時間を問わずに救急車は飛び込んでくるし、ナースコールも響き渡る。廊下で項垂れたまま背を撫でてもらっている人がいて、車椅子の上で顔を覆っている人がいた。きっとその人たちの家族や友人も、自分と同じ気分だろうと藍香は思った。
机の上でスマートフォンが震えだした。病院からの電話にあまりいい知らせはない。それでも出ないわけにはいかず、藍香は手に取って応答する。
「武蔵野七十字病院の福原です」
その口調で、もう嫌な予感がする。
「辻村です。お世話になっております」
「浩平さんの頭の中で、出血が起きてしまいました。血腫ができています。これから手術で取り除きたいと思います。ご同意いただけますか」
「またですか」
思わず、そう口をついて出てしまった。
【NOT FOR SALE】
試し読みの無断複製、転売、配布等は禁止します
©Atsuto Ninomiya / TO Books.
※この試し読みの内容は書籍収録内容と一部異なる場合がございます。
「最後の医者」シリーズのお買い求めはこちらから!

- 最後の医者は桜を見上げて君を想う
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(上)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:638円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(下)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:594円(税込)

- 最後の医者は海を望んで君と生きる
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)