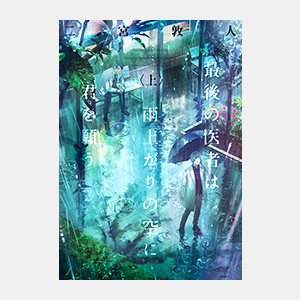- トップページ
- 最後の医者は海を望んで君と生きる(2/5)
試し読み
最後の医者は海を望んで君と生きる(2/5)
著:二宮敦人
救命救急センターに駆けつけた福原を見上げ、辻村浩平は弱々しく訴えた。
「どうか」
頷く福原に手を差し出し、蚊の鳴くような声で「どうかよろしくお願いします」と告げると、そのまま昏倒した。福原はストレッチャーに落ちた彼の手を取り、握りしめる。
「任せてください」
バイタルを確かめ、叫ぶ。
「一分一秒を争うぞ、急げ!」
看護師と一緒にストレッチャーを押し、猛然とカテーテル室へと走った。
「準備はいいか」
福原の呼びかけに、臨床工学技士が頷いた。彼の前にはキャスター付きの銀色の台、そして白い小ぶりの機械。あたりにはモニターが五つ、それぞれ数値やグラフが表示されている。細かい配線やチューブ、酸素ボンベの姿も見える。体外式膜型人工肺──心臓の代わりをするポンプと人工肺を備えた精密機械。命を救う、最後の砦だ。
「エクペラですよね」
「ああ、いつものインペラ併用で行く。まずV-A、右鼠径部から入れる」
すでに処置台には必要なものが全て準備されていた。消毒薬に消毒綿、エクモセット、ヘパリン生食シリンジ、そして補助循環用ポンプカテーテル。
インペラは、見たところ直径数ミリ程度の長い管に過ぎない。先っぽにかぎ爪のような形があるので、釣り針を連想する人もいるだろう。しかしその本質は、中に仕込まれた超小型のポンプにある。先端から血を吸い込み、後ろから吐き出すことで、心臓が血を運ぶ手伝いをするのだ。
エクモとインペラ。この二つの医療機器が、辻村浩平の心臓にとって杖となる。ふらふらとよろめき、今にも倒れそうになっているところを支え、死の淵から救うのだ。
福原は滅菌ガウンと滅菌手袋、そしてサージカルマスクを身につけ、手術帽をかぶった。看護師が超音波診断装置の前に立つ。
福原はスタッフ全員と素早く、しかし確実に視線を合わせてから告げた。
「劇症型心筋炎だ。このままだと心臓が止まり、彼は死ぬ」
一瞬、室内が静まりかえる。熾火に藁を投じるように、福原は宣言した。
「俺たちで絶対に助けるぞ」
スタッフの瞳に炎が燃え上がった。弾かれたように全員が動き出す。まず、患者のへその高さから両の膝あたりまで、消毒薬に浸した綿球で広範囲を消毒。そこに医療用ドレープという布をかける。
看護師が袋に包まれた、レジのバーコードリーダーのようなものを福原に手渡した。エコープローブである。福原がそれを患者の股関節のあたりに当てると、モニターに血管が二本、現れた。
大腿動脈と大腿静脈である。片方の道を辿って血が下半身へと向かい、もう片方の道を通って心臓へと戻ってくる。それぞれに管を差し込み、人間と機械とを繋ぐ。考えてみれば、実に荒っぽいやり方だ。だからこそ、作業は一つ一つ丁寧に、確実に進めなければならない。
福原は穿刺針を持つと、よどみない動きで一方の血管に刺し込んだ。注射筒を繋げ、軽く引いて血が上ってくるのを確認する。
「よし」
注射筒を取り外し、今度は細い針金のようなガイドワイヤを穿刺針の中を通して入れる。抵抗感はない。目的の血管にガイドワイヤが入ったのをモニターで確かめると、今度は管を入れていく。同じようにしてもう一方の血管にも管を入れた。
「接続よし」
福原は臨床工学技士を振り返った。
「クランプ解除する」
管に噛ませていたペアン鉗子を取り外す。
「運転開始します」
エクモのポンプが唸る。暗赤色の血液が管の中を通って流れ出した。
「フローはどうだ」
福原が流量について聞くと、臨床工学技士が答えた。
「フロー、四L取れてます」
一分間あたり四リットルの血液が筒状の人工肺に送られていく。張り巡らされた一万本の中空糸を通り抜けて血中のヘモグロビンが酸素を受け取ると、血は見るも鮮やかな赤色へと変わる。瑞々しい血は再び管を通って体へと戻り、全身を巡る。
「脱血圧、送血圧問題ありません」
「いいぞ」
軽く微笑んでから、福原はすぐに次の手順に移った。ガイドワイヤを心臓まで届かせた上で、インペラを入れる。全ての作業が終わると、心なしか患者の血色は良くなり、表情も穏やかになったようだった。
もう一度モニターを確認し、臨床工学技士が頷いた。
「問題ありません」
福原は軽く拳を握り込み、マスクの下で微笑んだ。スタッフたちも歓声こそ上げないが、みな明るい表情を浮かべる。
今、命は瀬戸際で繋ぎ止められたのだ。
†
電車の扉が開くなり、辻村藍香はプラットホームに飛び出した。
階段を駆け下り、案内板を確かめ、自動改札を抜ける。武蔵野七十字病院は南口を出た先、徒歩十分。
イルミネーションが煌めくバスロータリーを抜け、百貨店の前を駆けてゆく。ちらほら降っていた雪はすでに止み、微かに痕跡が街路樹の根本に残っているばかり。
あちこちからクリスマスソングが聞こえてくる。サンタクロース姿の店員が手を振っている。リボンの巻かれた大きな箱を抱えて、家路を急ぐ男性がいる。両親と手を繋いではしゃぐ子供がいる。腕を組んで歩く、仲睦まじい男女がいる。
どいて。道を空けて。
藍香は強引に人混みをかき分けて走り続けた。
やがて闇を背に、白い建物が姿を現した。敷地内に入ったところで藍香は足を止め、その七階建ての巨躯を仰ぎ見る。こんなに大きな病院に来たのは初めてだ。動悸がしている胸をしばらく押さえ、ハンカチで汗を拭うと、再び駆け出した。
どこから入ればいいんだろう。
大きな入口には「外来受付終了」と札が出され、電気が消えている。あたりに目を凝らし、ようやく救命救急センターと書かれた看板を見つけた。自動ドアから中に入ると、そこは半分廊下、半分待合室という雰囲気だった。エレベーターを待っている医師たちや車椅子に乗せられた患者、ソファで文庫本を開いている老婦人を横目に、真っ直ぐ受付に向かう。
「どうされましたか」
顔を出した女性に、身を乗り出して言った。
「辻村藍香と申します。ここに救急車で運ばれた、辻村浩平の妻なんですが」
声が震えそうになるのをこらえて続ける。
「さっき夫から電話を貰って。先生からもお話をいただいて、ここに来るようにと言われたんです」
女性は頷くと「少々お待ちください」と奥に引っ込んでしまった。その背に叫ぶ。
「あの、浩平は大丈夫なんでしょうか!」
返答はなかった。藍香はそのまま立ち尽くす。
あたりは不気味なほど静かだった。
さっきまで談笑していた医師たちはエレベーターに乗り込み、車椅子の患者は廊下の奥に消えていった。すぐそこに座っている老婦人は、本に目を落としたまま微動だにしない。
靴下を二重に履いているのに足先が冷えた。リノリウムの床から冷気が這い上がってくる。
ずいぶん長いこと待った気がした。
「辻村浩平さんのご家族の方ですね」
看護師が一人、廊下を早歩きで近づいてきた。
「はい」
「お待ちしていました。辻村さんはICUに移られました。先生からお話がありますので、こちらへどうぞ」
「ICU?」
「ご案内します」
言われるままに後に続き、エレベーターに乗る。二階で降りて少し歩き、扉の前で止まった。掲げられたプレートには「Intensive Care Unit」とある。
「先生を呼んできますので、お待ちください」
看護師だけが扉の中に消え、藍香はまたも一人、人気のない廊下で待たされる。ぷんと消毒薬の香りがして、ピッ、ピッという規則的な電子音が聞こえる。
やがて現れたのは、大柄な男性医師であった。
「お待たせしました。福原と申します。こちらの部屋でご説明しましょう」
小さな会議室のような空間に案内され、電気のスイッチを入れる音を聞いた時、藍香の足はすくんだ。これから何か恐ろしい言葉を聞かされるのだとわかった。
「どうぞ、お入りください」
福原の柔らかな声。入らないわけにはいかない。藍香は逃げ出したい衝動を必死に抑え、椅子に腰を落とした。
説明は簡潔明瞭なもので、頭ではすっと理解できたが、最後まで心が追いつかなかった。
心臓が止まりかけている。機械の力を借りて何とか生きている。危険な状態だが、元の生活に戻れるよう、全力で治療をしている……。
確かに風邪気味だったけれど、朝はあんなに元気で笑ってた。いつもと何も変わらなかった。それが、どうして急にこんなことに。
部屋を出て、ICU面会受付の前に立つ。
「お荷物はそちらのロッカーに。貴重品はお持ちください」
看護師に言われ、藍香は両手にずっと持っていたものを下ろし、ハンドバッグと一緒にロッカーに入れた。
右手に抱えていたのは大きな花束。紫、赤、黄色、白、色とりどり。花好きの彼に贈りたいと伝えたら、店員が見繕ってくれた。いい香りがする。
左手に提げていたのは紙箱。中の有様は想像したくない。あれだけ走ったのだ。限定販売のチョコレートケーキはぐちゃぐちゃだろう。
笑顔を運んでくるはずだったものが二つ、まだ己の使命を疑わぬ顔つきでロッカーに収まっている。藍香は目を逸らし、扉を閉めて鍵をかけた。軽い金属音が響いた。
「そちらで手指の消毒を。手首までしっかり洗ってください。それからサージカルマスクを着用していただきます」
事務的な口調の指示に従い、用意を終えてICU内に入る。奥のベッドの前で福原が待っていた。体中に管を繋がれた、いかにも重症という様子の患者が寝かされていた。
それが最愛の人、浩平だと気づくまで、藍香にはしばらくの時間が必要だった。
いつも明るくて、くるくる表情が変わり、大きな声で楽しそうに笑う彼の印象とはかけ離れていた。
顔色は悪く、薄目を開き、呆けたような口からは青い管が飛び出している。管は鼻からも出ていて、頰にテープで固定され、横の点滴棒へと続いている。体にかけられた薄いブランケットの下では、管の中を赤い液体が流れていた。ブーンと機械音が響いている。
こうくん。
目頭が熱くなるのを藍香は必死にこらえた。
可哀想に……。
福原が言う。
「今は鎮静剤が効いていて、眠っています」
藍香は頷き、傍らの白い装置と大きな酸素ボンベに目をやった。
「これが浩平を助けてくれる機械ですか」
「はい。ほとんど止まりかけている浩平さんの心臓の代わりに、全身に血液を送っています」
藍香はおそるおそる浩平の手に触れてみた。ちゃんと温かかったが、少しざらついた感触がした。
「目を覚ますまで、そばにいてあげたいんですが」
福原は申し訳なさそうに首を横に振った。
「お気持ちはよくわかりますが、ICUの面会は十五分程度でお願いしているんです。今日は一度帰ってしっかり休んで、また明日いらしてください」
「でも、もし何かあったら」
「スタッフが常に患者さんをチェックしていますから、何かあればすぐ対応します。それにこれからのことを考えると、藍香さんも体を休めておいた方がいいと思います」
「これからって何ですか。これから、どうなるって言うんですか」
藍香はほとんど泣きそうだった。
「回復まで少し時間がかかるかもしれない、という意味ですよ。今はともかく命を繋ぎとめたところです。お若いので、おそらく数日で持ち直すでしょう。そうしたら装置も外せますし、ICUからも出られますよ」
福原は落ち着いた声で続けた。
「ご安心ください。必ず、助けます」
その目には決意の光が見て取れた。
それでも藍香の不安は完全には取り払われない。
本当に大丈夫なんですか。助かるんですよね。そうしつこく聞きたい。だが、相手は同じ言葉を繰り返すしかないのだろう。
浩平と医者とを交互に見てから、藍香は頭を下げた。
「何卒よろしくお願いします」
声が震えた。こんなに心配なのに、自分には何もできない。呆れるほどに無力だった。
「お任せください」
福原は力強い声で答えてくれた。
【NOT FOR SALE】
試し読みの無断複製、転売、配布等は禁止します
©Atsuto Ninomiya / TO Books.
※この試し読みの内容は書籍収録内容と一部異なる場合がございます。
「最後の医者」シリーズのお買い求めはこちらから!

- 最後の医者は桜を見上げて君を想う
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(上)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:638円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(下)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:594円(税込)

- 最後の医者は海を望んで君と生きる
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)