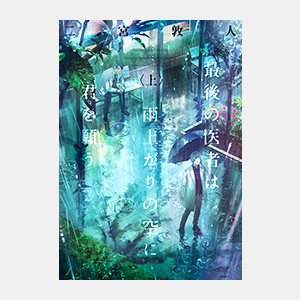- トップページ
- 最後の医者は海を望んで君と生きる(3/5)
試し読み
最後の医者は海を望んで君と生きる(3/5)
著:二宮敦人
帰りの電車に揺られながら、藍香はスマートフォンで色々調べてみたが、福原が教えてくれた以上の情報は出てこなかった。すぐ横では学生がゲームに没頭していて、目の前のサラリーマンは本を読んでいる。こんなことを必死に調べているのは車内で自分一人かもしれないと思うと、急に心細くなった。
中野駅に着いた。改札を出て、朝は浩平と一緒に歩いた道を逆にたどる。
頭の中では不安が渦巻いている。何を見ても、恐ろしい想像へと繋がってしまう。並木道の桜、また二人で見られるだろうか。あのコンビニに二人で行くのは、あの日が最後になったりはしないだろうか。思わず悲鳴を上げそうになるたび、藍香は自分に言い聞かせた。
考えるな。今はただ、家に帰ることだけに集中するんだ。
ようやく自宅に辿り着いた時には、疲れ果てていた。いつもの習慣で「ただいま」と言ったが、誰からも「おかえり」はない。家の中には闇と静寂が広がっている。
明かりをつけ、ダイニングテーブルに花束とケーキの箱を放り出すと、藍香はコートも脱がずにソファに倒れ込んだ。深く息を吐き、掌で顔を覆った。しばらくそのまま動けなかった。
やがて「よし」と腹から声を出し、立ち上がった。
しっかりしないと。こうくんは今も頑張っているんだから。
コートとスーツをハンガーにかけて、シャツは洗濯籠に。風呂に湯を張り、花束は茎の先をハサミで切って花瓶に活け、ケーキは箱ごと冷蔵庫にしまった。買い込まれていた鶏肉や野菜を適当にぶつ切りにして鍋に放り込み、水を入れて加熱する。
食欲はないけど、栄養は取っておかなくちゃ。
煮立ったところで味噌を溶き、具だくさんの味噌汁にして、ご飯と一緒に胃に流し込む。適当に味付けした割には、美味しかった。
こうくんは、何か手の込んだ料理を作るつもりだったんだろうな。
再び暗い気持ちが頭をもたげたのを、慌てて振り払う。
挫けるな。やるべきことをやるんだ。
まずは入院の準備。病院で渡された冊子を読み、着替えや洗面用具などを鞄に詰め、書類に必要事項を記入する。
あちこちに連絡もしなければ。ノートにリストアップして、順番に電話をかけていく。浩平のご両親。彼が勤務しているイベント会社。それから自分の両親と、会社の上司──。
「そういうわけで明日は病院に行ってから出社しますので、午前休にしてもらえますか。それから、しばらく残業はできるだけ減らしたいんです。勝手な物言いですみません」
電話の向こうでは部長の声に交じって子供の笑い声がした。
「大変なことになったね。仕事はみんなで少しずつ巻き取るよ。残業なんかしちゃいけない。とにかく今は彼のそばにいてあげて」
「ありがとうございます」
スマートフォンを耳に当てたまま、藍香は深々と頭を下げる。
「何なら、しばらく休みを取ってもいいんだぞ」
「面会時間が限られてまして。その間家にいても、憂鬱になっちゃうだけですから」
「そういうものか。じゃあお花やお見舞いも、今は避けた方がいいかな」
「そうですね」
「わかった、みんなには私から伝えておくよ」
楽しそうな声が聞こえてきた。
パパ、靴下はどこにつけたらいいの? サンタさんへのお手紙は? こら、パパはお仕事中だから後にしなさい。
「騒がしくてすまないね、とにかく仕事の心配はしなくていいから。細かいことは、また会社で」
「色々とすみません」
「困った時にはお互い様だよ。じゃあ、また」
ちょっと、パパの机を使うなら端っこでね。ほら、先に食べちゃいなさい、それ。
部長の猫なで声を最後に、電話は切れた。
関係各所への連絡には、一時間以上かかった。リストを確かめ、藍香は深呼吸して伸びをする。
これで最低限伝えておくべき人には伝えられたかな。
みんな優しくしてくれて、嬉しかった。
浩平の上司は「元気に戻ってくるのを待っています」と言ってくれた。義父は「きっと大丈夫、助け合って乗り越えましょう」と励ましてくれた。これまではちょっと苦手な印象のあった義母も「まずは藍香さんも、きちんとご飯を食べて体を休めるようにしてください」と気遣ってくれた。
こんな時は、周りの人の存在が心強いな。自分の両親だけは慌てふためいていたので、こちらがなだめなくてはならなかったけど。
一段落したのでお風呂にでも、と思った時、スマートフォンが震えた。
「ねえねえ、春くらいにまた海行かない?」と呑気なメッセージを送ってきたのは大学時代からの親友、中田祥子だった。藍香は苦笑しつつ、返事の代わりに電話をかける。
祥子にも伝えておくべきだろう。浩平と出会えたのは、彼女のおかげなのだから。
「うそ、ほんとに? 大変だったでしょう、お疲れ」
目をひん剝いて驚く祥子の顔が、ありありと想像できた。
「藍香、くれぐれも元気出してね。いやそうもいかないか。そうだよね、言われて元気出れば苦労ないもんね、私だったらそう。でも、ああ、ごめん、何て言ったらいいかわかんない、私の方が動揺しちゃう」
祥子は社会人四年目になっても、相変わらず思ったことが全部口から出てしまうようだ。
「気持ちは伝わってるから。ありがとね」
「一人だからって外食ばかりじゃだめだよ。人間は口に入るものでできてるんだからね。ちゃんと自炊すること」
彼女らしからぬ物言いに、思わず噴き出してしまった。
「私たちは二人とも料理するから、いつも自炊だよ。おおかた祥子がそう言われてるんでしょう」
「やっぱりわかる? 私料理って苦手でさあ。だから料理好きな人と結婚したのに、お前もできるようになっとけ、だって。それでこないだオムライスを教わったの」
「恒樹さんはお元気? 披露宴で会ったきりだけど」
「元気、元気。うるさいくらい」
「いいことだよ。くれぐれも気遣ってあげてね」
「そうね。浩平君みたいに急に倒れられても困るし。あっ、いや、違うの。その、悪い意味じゃなくて」
「わかってるよ」
藍香は笑って受け流した。
「それにしても怖いね、その、心筋炎だっけ? 急に入院なんて」
「風邪が長引いてて、変だとは思ってたんだけどね。甘く見てたよ」
ため息をつくと、部屋の灯りがちらついた。
「休むように何度か言ったんだけど。こうくんはこれくらい平気だからって……今思えば、無理してたのかな」
「浩平君ってそういうとこあるよね。そんなに丈夫じゃないくせに」
「明るく振る舞うのはいいんだけど、弱いところを見せないんだよ。そういう人だって知ってたのに」
スマートフォンを握る手が震えた。
「私がちゃんとしていれば。早めに休ませて、しっかり治していれば、こんなことには」
一つ、嗚咽が漏れる。歯を食いしばる。
「藍香?」
「ごめん。ちょっと、無理。変なスイッチ、入った」
鼻の奥がつんとして、視界がぼやけてきた。熱い涙と一緒に口から言葉が零れ出す。
「なんか、家のことやってても、いないの。玄関に靴がないんだよ。洗う食器はいつもの半分だし、オーディオセットも止まったまま。でも洗濯籠には昨日の服が入ってて、トイレットペーパーは斜めにちぎり取られてて。朝作ってくれたコーヒーも、ポットにまだ残ってるの、冷たくなって。でもいない、いないんだよ。こんなことある? おかしいよ。私、知らない世界に迷い込んじゃったみたい」
自分は一体何を言っているんだろう。
相手が祥子だから、つい心が緩んだのかもしれない。ぼろぼろと床に落ちる涙を、藍香は他人事のように眺めていた。
「でもね祥子、わかってる。私はわかってるよ、こうくんは入院してるんだから、いないのは当たり前だよ。だけどふいに怖くなる。このまま、この世界が終わらなかったらどうしようって」
「藍香、ちょっと」
「電話があったの。帰る途中に、いきなりの電話。こうくんがね、万が一のためだって、普段は言わないようなことを言うの。真剣な声だった。もしあの電話が最後だなんてことになったら、私、私……」
声がかすれた。
「藍香!」
祥子の叫びで我に返る。
「落ち着いて、大丈夫だよ。浩平君は救急車で運ばれて、病院でちゃんと治療してもらってる。間に合ったんだよ。危なかったけれど、助かったんだ。良かったじゃない」
「良かった……の?」
「そうだよ。だから風邪はこれから気をつければいいの。浩平君だって懲りたと思う。そんなこともあったねって、そのうち笑い話になるよ。きっと」
「そうだね」
藍香は一つ洟をすする。さっきあれほど流れていた涙は、嘘のように止まっていた。
「藍香、前向きに考えようよ。そうだ、退院したら、みんなで海に行こう。浩平君とまたダイビングしたらいいよ。私たちは波打ち際で遊んでるけど。恒樹、泳げないんだよね。太ってる人は浮かぶから平気だって言ったんだけど、怒るのなんの。俺は太ってない、骨太なんだって」
ふっ、と笑いが出る。
「ありがとね、祥子」
「お礼はやめてよ、友達じゃない。私でよければいつでも話聞くからね」
一人には広すぎる家の中、祥子の明るさはありがたかった。
「じゃあ、お大事に。外食ばかりじゃだめだよ、栄養偏るから。じゃあ、また」
電話は切れた。
「自炊してるってば」
藍香はスマートフォンを充電器に繋ぎ、残った味噌汁をプラスチック容器に移して冷蔵庫へ入れる。シャツにアイロンをかけ、寝床を整えてから、ゆっくりと風呂に浸かった。髪を乾かし終えてから、小さなライトを一つだけ点けて、ベッドに入る。
早くこうくんの心臓が元気になりますように。
祈りながら目を閉じた。
†
福原が様子を見にICUに来た時には、すでに藍香がベッドのそばで浩平の寝顔を見つめていた。
「こんにちは、藍香さん」
軽く会釈して話しかける。
「あ、福原先生。いつもありがとうございます」
「いえ」
浩平の容体は依然として不安定だった。少し良くなっても、すぐにまた戻ってしまう。それくらいは想定の範囲内ではあったが、微かな焦りも感じないではない。
何よりも、入院してから毎日見舞いに来ては、意識のない浩平の手に触れたり、耳元に何か話しかけたりしている藍香の姿を見ると、胸が締め付けられるのだった。
「浩平さん、昨夜は少しですが意識が戻られてましたよ」
気休めに近かったが、福原は声をかけた。
「そうなんですか」
こちらを見て、ほっとしたように笑う藍香。
「はい。こちらを見て瞬きされてました。今眠くなるお薬を入れてますから、と伝えると軽く頷いて、また眠ったようです」
「じゃあ、良くなってるんですね」
「ええ。少しずつですが」
良かった、と藍香が呟き、視線を戻す。まさにその時だった。
浩平が微かに呻き、薄目を開けた。
「あっ。こうくん」
これには福原も驚いた。だが、まぶたが開いたのはほんの少しだけで、そのまま動こうとしない。まだ眠り続けているようだ。
「私だよ。わかる? 良かった、こうくん!」
それでも藍香は喜んでいた。浩平の前に顔を突き出し、しきりに話しかけている。しばらく福原は微笑ましい思いで二人の様子を眺めていたが、ふいに言い知れぬ違和感に体が動いた。
「失礼します」
はしゃいでいる藍香を押しのけ、ベッドに覆い被さるようにして浩平の瞳を覗き込む。
まずい。
浩平の目が左右で違っていた。左の瞳だけが大きい、いや今も少しずつ大きくなっていく。猫の瞳が闇で開くように。
「瞳孔不同だ」
近くの看護師を振り返り、福原は叫んだ。
「頭の中を見たい。今すぐCTスキャン、ねじ込んで。それから高張食塩水を投与、急げ!」
「はい」
看護師が一人、電話をかけ始める。別の看護師がベッドの横で移動の準備を始めた。福原もそれを手伝う。急に慌ただしくなった室内で、ただ藍香だけが何が起きているのかわからず、震えながら立ち尽くしている。
福原は藍香のそばに近づき、額の汗を拭いてから伝えた。
「すみません、状況が変わりました。後ほどご説明にうかがいます。しばらく別室でお待ちください」
柔らかく言おうと意識してはいるのだが、どうしても張り詰めた声になってしまう。
「はい」
藍香の顔は蒼白で、唇は紫色に染まり、微かに歯の鳴る音がする。それでも福原は言うしかなかった。
「検査をしてみないとわかりませんが、この後、緊急手術になるかもしれません」
「はい」
「辻村さんを案内してあげて」
【NOT FOR SALE】
試し読みの無断複製、転売、配布等は禁止します
©Atsuto Ninomiya / TO Books.
※この試し読みの内容は書籍収録内容と一部異なる場合がございます。
「最後の医者」シリーズのお買い求めはこちらから!

- 最後の医者は桜を見上げて君を想う
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(上)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:638円(税込)

- 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(下)
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:594円(税込)

- 最後の医者は海を望んで君と生きる
- 著:二宮敦人
イラスト:syo5 - 定価:715円(税込)